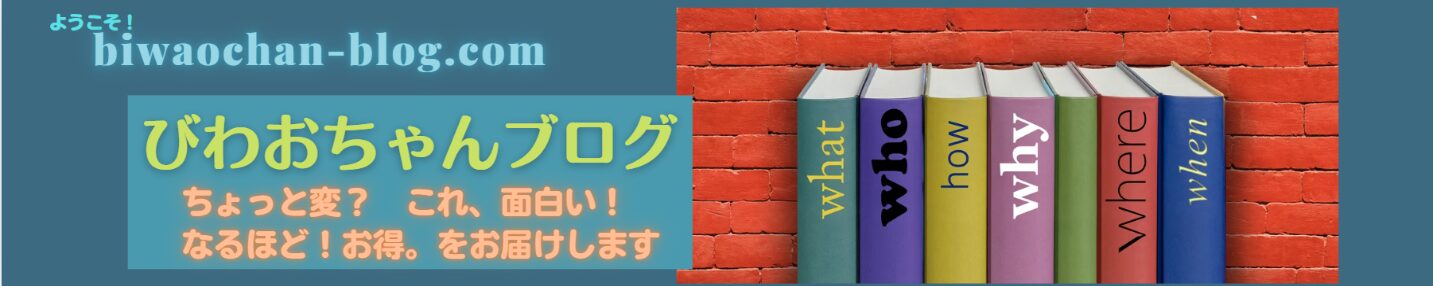こんにちは!びわおちゃんブログにようこそ。
連日、メディアを賑わせている大阪・関西万博。2025年8月20日、ついに一般来場者数が1500万人を突破したというニュースが飛び込んできました。
👉万博の一般来場者が1500万人突破、開幕から130日目…会期終盤は駆け込みで増える予想
これは2005年の愛知万博を上回るペースだそうで、会場の熱気が伝わってくるようです。さらに、運営費の収支が黒字になる目安とされていた入場券販売枚数約1800万枚も8月上旬には達成し、運営の黒字化がほぼ確実になったとのこと。開催前には建設の遅れや費用の高騰、不祥事などで厳しい声も聞かれ、「本当に開催できるのか」「赤字になるのではないか」といった懸念が渦巻いていただけに、運営に携わってきた方々の胸中はいかばかりかと拝察いたします。
数字の上では、まさに「大成功」への道をひた走っているように見えます。SNSには連日、来場者の楽しげな写真や動画が溢れ、公式キャラクター「ミャクミャク」のグッズは品薄になるほどの人気ぶりだとか。僕は万博には行っていませんが、「レンタカーを使わない旅」の乗り換えで伊丹空港に2回ほど行ったので、空港売店でこの姿をたくさん見ることができました。今回の記事、実際は万博に行ってはいないけれど「レンタカーの旅」の番外編としてあなたに読んでもらいますね。

黒字化という「成功」の甘い響き、その裏側で
まずは、この「黒字化」というニュースから見ていきましょう。これは間違いなく、素晴らしい成果です。国家的な巨大プロジェクトが赤字を垂れ流すことなく、自らの運営費を賄える見通しが立ったのですから、その手腕は評価されて然るべきでしょう。
しかし僕は一歩立ち止まって考えてみたいのです。この「黒字化」という甘美な響きと、来場者数という分かりやすい指標をもって、私たちは「万博は成功した」と手放しで喜んでしまってよいのでしょうか。祝祭の熱狂の中で、私たちが忘れてはならない、あるいは見過ごしてはいない大切な問いがあるのではないでしょうか。このブログでは、この一大イベントが本来果たすべきだった「使命」とは何だったのか、そして私たちはこの経験から何を学び、未来に何を手渡すべきなのかを、少しだけ深く掘り下げて考えてみたいと思います。

数字がもたらした安堵感と新たな問い
日本国際博覧会協会(万博協会)が発表したところによると、8月8日時点で入場券の累計販売枚数が損益分岐点である約1800万枚を超えました。運営費約1160億円の多くを入場券収入で計画していたため、これでひとまず赤字運営は回避できるというわけです。開催前、万博を批判的に報じていたメディアに対して、「結局黒字化じゃないか」といった声が上がるのも、ある意味では自然な反応かもしれません。
この「黒字化」という事実は、多くの関係者に安堵感をもたらしたことでしょう。そして、この成功は、今後の国際的なイベントを日本で開催する上での大きな自信にも繋がるかもしれません。しかし、この数字の達成を万博そのものの「成功」と定義づけることには、一抹の危うさを感じずにはいられません。
そもそも、この損益分岐点は、あくまで「運営費」に対するものです。会場建設費の上振れなど、私たちの税金が投入された部分についてはまた別の議論が必要です。そして何より、国際博覧会というイベントの価値は、会計報告書の最終的な数字だけで測られるべきではないはずです。私たちは、果たして「黒字になるイベント」を望んでいたのでしょうか。それとも、そこにはもっと違う価値や意味を求めていたのでしょうか。数字の達成という分かりやすいゴールに安堵するあまり、本来の目的を見失ってはいないでしょうか。

私たちは「何」に対してお金を払ったのか
チケット販売の最終目標は2300万枚、総来場者数は2820万人を想定しているそうです。多くの人がチケットを買い、会場へ足を運んでいる。それは紛れもない事実です。飲食や物販も好調で、保守的に見積もっても一人あたり600円が主催者の収益になるという試算もあります。
来場者は、パビリオンでの驚きや、世界各国の料理、そしてここでしか手に入らないグッズといった「体験」にお金を払っています。その一つひとつが積み重なり、結果として「黒字化」という目標を達成した。それは素晴らしい循環です。

しかし、ここで改めて問いたいのです。大阪・関西万博が掲げた壮大なテーマは「いのち輝く未来社会のデザイン」でした。私たちは、このテーマを体験するためにチケットを購入したはずではなかったでしょうか。もちろん、テーマパークのように楽しむことが悪いわけではありません。ですが、もし多くの来場者が感じた価値が、瞬間的なエンターテインメントや消費活動に留まるのであれば、それは果たして「未来社会をデザインする」という万博の使命を果たしたことになるのでしょうか。
運営の黒字化は、あくまでイベントを安定的に開催するための「手段」であったはずです。それがいつしか「目的」そのもののように語られ、その達成をもってすべてが良しとされてしまう風潮があるとしたら、それは本末転倒と言わざるを得ません。私たちが支払った対価は、単なる入場料ではなく、未来へのビジョンに対する投資であったはず。その投資が、どのような形で私たちの社会に還元されるのか。そのリターンについて、私たちはもっと関心を持つべきなのかもしれません。
喧騒のなかのリアルな「声」―来場者体験が映し出す光と影
次に、会場に足を運んだ人々の「声」に耳を傾けてみましょう。今回の万博は、まさに「SNS万博」とも呼べる様相を呈しています。その評価は、開幕前と後で劇的に変化しました。
SNSが紡いだ「攻略法」と熱狂
開幕前、万博を取り巻く空気は決して良いものではありませんでした。会場建設の遅れやメタンガス爆発事故の報道、増え続ける費用への批判など、SNS上には「万博は不要」「興味なし」といったネガティブな言葉が溢れていました。前売り券の販売も伸び悩み、先行きを不安視する声が大半を占めていたことは、記憶に新しいところです。
ところが、いざ開幕してみると、その空気は一変します。実際に会場を訪れた人々が発信する、臨場感あふれる「生の声」がSNSを駆け巡りました。特に特徴的だったのは、複雑な予約システムや広大な会場をいかに効率よく楽しむかという「攻略法」の共有でした。どのパビリオンが予約なしで楽しめるか、どのルートを通れば混雑を避けられるか、どのフードが美味しいか。そうした情報が瞬く間に拡散され、来場者の体験をより豊かなものにしていったのです。
これは、従来のメディアが発信する情報とは全く異なる、ユーザー主体の新しいイベントの楽しみ方と言えるでしょう。ある意味で、運営側が用意した楽しみ方をなぞるだけでなく、来場者自身が能動的に万博を「攻略」し、その体験を共有することで、新たな熱狂を生み出していったのです。この現象は、今回の万博が持つポジティブな側面の一つとして、特筆すべきことだと思います。

「満足」の裏にある、置き去りにされた不便と不安
来場者アンケートでは約8割が満足と答えるなど、高い評価を得ていることも事実です。多くの人が、世界の文化に触れ、未来の技術に驚き、素晴らしい体験をしたことでしょう。しかし、その華やかな「満足」の声の裏で、見過ごすことのできない不便や不安の声が上がっていたことも、私たちは忘れてはなりません。
「並ばない万博」を標榜していたにもかかわらず、人気パビリオンや記念撮影スポットには長蛇の列ができました。複雑な予約システムは、デジタル機器の操作に慣れていない人々にとっては高いハードルとなったかもしれません。夏の厳しい暑さ対策や、会場内の移動のスムーズさなど、運営面での課題を指摘する声も少なくありませんでした。
もちろん、これほど大規模なイベントで、すべての来場者を完璧に満足させることは不可能でしょう。日々のオペレーションを改善していく現場の努力には、本当に頭が下がります。しかし、寄せられる不満の声を単なる「個人の感想」として片付けてしまうのではなく、その一つひとつに耳を傾け、なぜそうした声が上がるのかを真摯に分析することが、より良いイベントを創り上げる上で不可欠ではないでしょうか。「8割の満足」を誇るだけでなく、「2割の不満」にこそ、未来への改善のヒントが隠されているのかもしれません。
あの夜、私たちは何を試されたのか―交通麻痺が暴いた脆さ
そして、万博の運営における問題を語る上で、2025年8月13日の夜に起きた出来事を避けては通れません。会場と市内を結ぶ唯一の鉄道路線である大阪メトロ中央線が停電によりストップし、約3万人もの人々が帰宅困難に陥ったのです。体調不良を訴える人も続出し、まさに会場は「孤島」と化しました。
NHKニュース:大阪・関西万博 運転見合わせで帰宅困難 協会「情報発信課題」
この一件は、夢洲という人工島に大規模なイベント会場を建設することの脆弱性を、最も厳しい形で露呈させました。危機管理体制や来場者へのサポート体制についても、多くの疑問の声が上がりました。
さらに問題視されたのは、その後の対応です。混乱のさなか、SNSでは「オールナイト万博」という言葉がトレンド入りし、一部の人々がその状況を楽しんでいるかのような投稿をしました。それに乗じるように、一部の関係者から好意的なポストが見られたことには、強い違和感を覚えた人も少なくないでしょう。多くの人が不安な夜を過ごしている中で、その状況を軽々しく扱うかのような姿勢は、当事者意識の欠如を指摘されても仕方ありません。一体、誰のための万博だったのか。この問いが、最も重く突きつけられた夜でした。
このトラブルは、単なる「不運な事故」ではありません。それは、巨大イベントを運営することの責任の重さと、来場者の安全を確保するという最も基本的な使命が、いかに重要であるかを、私たち全員に再認識させる出来事だったのです。
我々は万博に何を求めていたのか―イベントの本質への問い
黒字化の見通しが立ち、来場者も順調に増えている。しかし、その裏には数々の課題や問題も存在する。では、私たちはそもそも、この大阪・関西万博という巨大なイベントに何を求めていたのでしょうか。その原点に立ち返ってみたいと思います。
「いのち輝く未来社会のデザイン」はどこにあったのか?
繰り返しになりますが、今回の万博のテーマは「いのち輝く未来社会のデザイン」です。なんと壮大で、希望に満ちたテーマでしょうか。気候変動、貧困、パンデミックといった地球規模の課題に直面する私たちが、国や文化の違いを超えて、より良い未来を共に創り上げていく。そのためのアイデアや技術、そして対話の場となることが、この万博に課せられた最大の使命だったはずです。
では、実際に会場を訪れた人々は、このテーマをどれだけ実感できたのでしょうか。素晴らしいパビリオンや展示があったことは間違いありません。しかし、それらが個別のエンターテインメントとして消費されるだけでなく、「未来社会のデザイン」という大きな文脈の中で、一つの意味あるメッセージとして来場者に届いていたでしょうか。
万博協会の石毛事務総長は、開幕前のインタビューで「万博の成功とは何か」と問われ、想定来場者数は準備のための数字で目標ではないとし、成功の指標は来場者数ではなく、出展者と来場者の「満足度」であり、万博の意義を来場者に理解してもらうことだと語っていました。この言葉は非常に重要です。しかし、現状の評価軸は、どうしても「来場者数」や「収支」といった分かりやすい数字に偏りがちです。本来問われるべき「万博の意義の理解度」や「未来へのインスピレーション」といった、目に見えない価値を、私たちはどのように測り、評価すればよいのでしょうか。その方法論を持たないまま、ただ祝祭の喧騒に身を任せているだけだとしたら、あまりに勿体ないことではないでしょうか。
批判もまた、関心の一つの形
開催前から、万博には多くの批判が寄せられました。その中には、感情的なものや、事実に基づかないものもあったかもしれません。しかし、その多くは、この巨大プロジェクトに対する国民の関心の高さの裏返しでもあったはずです。なぜこれほど多額の税金が使われるのか。環境への負荷は大丈夫なのか。本当に私たちの未来のためになるのか。そうした真っ当な疑問や懸念が、「批判」という形で表出していたのです。
SNS上で、万博を批判する人々と擁護する人々が激しく対立する光景も、幾度となく見られました。しかし、「批判」をすべて「ネガキャン」や「足を引っ張る行為」として切り捨ててしまうのは、あまりに短絡的です。建設的な批判は、物事をより良い方向へ導くための重要なエネルギーとなり得ます。運営側は、そうした声にも真摯に耳を傾け、対話を重ねる努力が必要だったのではないでしょうか。そして私たちもまた、白か黒か、賛成か反対かという二元論に陥るのではなく、なぜそのような意見が出てくるのか、その背景にある問題は何かを冷静に考える「批判的思考(クリティカルシンキング)」が求められていたのかもしれません。
無関心こそが、最大の敵です。その意味で、良くも悪くもこれだけ多くの人々が万博について語り、議論したという事実は、それ自体に価値があったと言えるかもしれません。
1970年の幻影と、2025年のレガシー
大阪の万博といえば、多くの人が1970年の大阪万博を思い起こします。6400万人以上という驚異的な来場者数を記録し、「人類の進歩と調和」をテーマに、戦後日本の高度経済成長を象徴する一大イベントとして、今なお伝説的に語り継がれています。

しかし、ある専門家は、1970年が関西の経済的な地位のピークであり、その後は長期的な低落傾向が続いたと指摘しています。つまり、イベントとしては大成功だったものの、それが持続的な経済的レガシー(遺産)に繋がったかという点では、反省の余地があるというのです。
今回の2025年万博は、その反省の上に立たなければなりません。一過性の祭りで終わらせるのではなく、この勢いを関西、ひいては日本全体の成長の起爆剤に繋げていくことが強く求められています。ライフサイエンスや脱炭素といった分野での産業競争力の強化、世界各国とのネットワークの構築、そして未来を担う子どもたちへの教育的な価値の提供。そうした具体的なレガシーを、私たちは生み出すことができるのでしょうか。夢洲の跡地利用の問題も含め、万博が終わった後こそが、本当の挑戦の始まりなのかもしれません。
結論―祝祭のあとに、私たちに残されるもの
大阪・関西万博は、来場者1500万人を突破し、運営の黒字化も視野に入ってきました。数字の上では、紛れもない「成功」と言えるかもしれません。しかし、この記事を通じて私たちが考えてきたように、その成功という言葉の裏には、数多くの問いが隠されています。
黒字化は、万博という壮大な物語のハッピーエンドではありません。それは、最低限の目標をクリアしたという、ほんの始まりに過ぎないのです。本当の成功とは、この万博を通じて、私たちの社会が、そして私たち一人ひとりの意識が、どのように変わったかで測られるべきものです。

「いのち輝く未来社会のデザイン」というテーマは、誰か偉い人が設計図を描いてくれるものではありません。それは、この万博を体験した私たち一人ひとりが、日々の暮らしの中で、考え、行動し、対話し、そしてデザインしていくべきものなのです。万博は、そのための壮大な問題提起であり、インスピレーションの源泉であったはずです。
閉幕の日は、刻一刻と近づいています。この祝祭が終わったとき、私たちの手元に何が残るのでしょうか。美しい思い出や楽しい記憶でしょうか。それも素晴らしい財産です。しかし、それだけでは足りないのです。なぜ、この時代に、この場所で、万博は開催されなければならなかったのか。その根源的な問いに対する、自分なりの答え。そして、より良い未来をデザインしていくための、小さな、しかし確かな意志。それこそが、この巨大なイベントが私たちに残すべき、最も価値あるレガシーなのではないでしょうか。
さて、閉幕まであとわずか。私たちはこのイベントから、何を受け取り、何を未来へ手渡すのでしょうか。その答えは、私たち一人ひとりの心の中にあります。
☆☆☆☆☆今日はここまで。
使用した写真は大阪・関西万博公式サイトから転載しました。
👋👋👋
【旅関連はこっちから】
【アニメ関連はこっちから】
びわおちゃんブログをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。