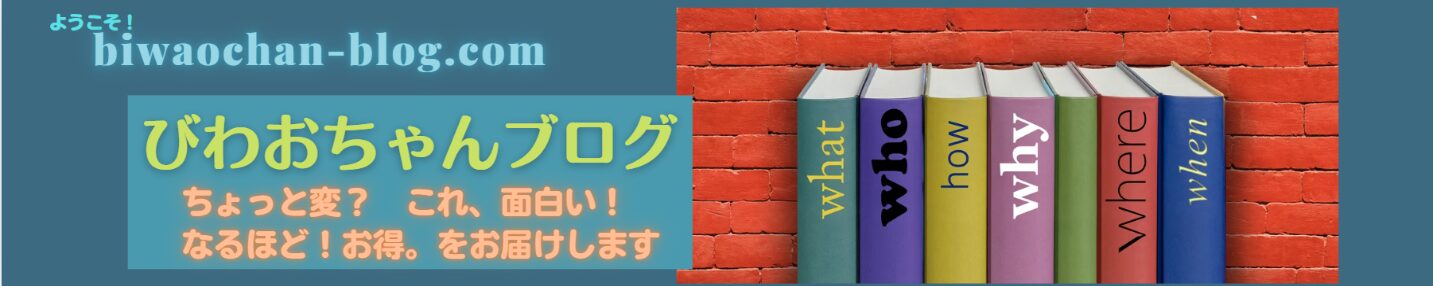こんにちは!びわおちゃんブログ&アニオタWorld!へようこそ。
毎日、本当にお疲れ様です。仕事や人間関係の中で、気づけば心のどこかが少しだけすり減ってしまっている。そんな感覚に陥る夜はありませんか?
ぼくのブログでは『薫る花は凛と咲く』の第1話の感想を書いてから、少し時間が経ってしまいました。凛太郎と薫子、二人のあまりにもピュアな世界の尊さに胸を焦がしつつも、その完成された関係性を言葉にする難しさに、正直なところ筆が止まっていたのです。
しかし、物語はずっと追い続けていました。そして、ついに迎えた第6話「大嫌い 大好き」。
このエピソードは、僕の躊躇を、そしておそらくは多くの視聴者の固定観念をも打ち砕く、まさに「神回」でした。凛太郎と薫子の世界に、保科昴というもう一人の主人公が加わったことで、物語は一気にその奥行きを増し、私たちの心の最も柔らかな部分を揺さぶる、魂のドラマへと昇華したのです。
今回の記事は、この歴史的な第6話の感想・解説がメインです。しかし、その深い感動を余すことなく味わっていただくために、まずは第6話がなぜ「特別」なのか、その核心に触れていきたいと思います。
この記事が、あなたの乾いた心に優しく染み渡り、明日への温かい光となることを願って。しばし、物語の世界へご一緒ください。
タイトル「大嫌い 大好き」が照らし出す、三つの心の交錯
このあまりにも印象的なタイトルは、誰が誰に向けた言葉なのでしょうか。物語を深く味わうために、まずはこのタイトルが象徴する三組の関係性について、紐解いていきましょう。
親友への愛憎【昴と薫子】―愛ゆえの過ちと、拭えない自己嫌悪
物語の中心にいるのは、紛れもなく昴から薫子への想いです。彼女が凛太郎に「会わないで」と頼んだのも、薫子を想うがゆえの行動でした。しかし、その方法が間違っていたこと、そして何より、親友を裏切るような形になってしまった自分自身が「大嫌い」。それでも、心の底から薫子のことが「大好き」。このどうしようもない矛盾こそが、昴を苛む苦しみの正体です。愛と憎しみが、親友ではなく自分自身の中で渦巻く、痛切な関係性です。

隔てる壁と繋ぐ心【薫子と凛太郎】―信じる力が育む、混じり気のない愛
薫子にとって、凛太郎は「大好き」な人。しかし、彼らの間には「千鳥」と「桔梗」という、世間の偏見が作り出した壁があります。薫子はその「壁」や、それを作る人々、そしてそれによって凛太郎を判断してしまう風潮が「大嫌い」なのでしょう。彼女の凛太郎への想いは、そうしたノイズを一切排した、彼の本質だけを見つめる純粋な「大好き」です。この二人の関係性は、物語の根幹をなす光そのものです。

鏡合わせの誠実さ【昴と凛太郎】―敵意を超えて響き合う、魂の共鳴
当初、昴にとって凛太郎は、大切な薫子を脅かす存在として「大嫌い」な対象でした。しかし、彼もまた自分と同じように、ただひたすらに薫子の幸せを願う誠実な人間だと知った時、その感情は大きく揺らぎます。凛太郎の底抜けの優しさと誠実さに触れた時、昴の中に芽生えたのは、敵意ではなく、尊敬や共感に近い感情だったはずです。それはまだ「大好き」とは呼べないかもしれない。けれど、かつての「大嫌い」が、確かに温かい何かへと変わった瞬間でした。
物語が大きく動いた瞬間~第6話「大嫌い 大好き」あらすじ

それでは、この心を揺さぶる第6話の物語を、3つのシーンに分けて振り返っていきましょう。
親友への告白―罪悪感に揺れる昴と、全てを包む薫子の優しさ
物語は、昴が薫子を公園に呼び出し、凛太郎に「会わないでほしい」と頼んだことを告白するシーンから始まります。何度も「ごめんなさい」と繰り返す昴。彼女は、薫子に絶交されても仕方がないと覚悟していたでしょう。しかし、薫子の反応は予想外のものでした。「私のためなんでしょ。昴は優しいね。心配かけてごめんね」。責めるどころか、昴の行動の裏にある優しさを見抜き、感謝と謝罪の言葉を口にする薫子。そのあまりにも大きな愛を前に、昴は安堵すると同時に、そんな自分を許せないという深い自己嫌悪に陥っていくのでした。

過去と現在が繋ぐ絆―「今だけ、昔に戻ろう」という魔法の言葉
「ああ、私は最低だ」。罪悪感に押しつぶされそうになる昴に、薫子は「今だけ、昔に戻ろうよ!」と、夜の公園で無邪気に遊び始めます。そこで語られる、幼い頃の思い出。うんていから落ちた薫子を見て、自分のことのように泣き、「痛いの全部昴に飛ばしていいから」と言った小さな昴。薫子はその頃からずっと、昴の優しさを知っていました。「私が好きな昴を、昴が否定しないでよ」。薫子のまっすぐな言葉と抱擁は、頑なに閉ざされていた昴の心を、少しずつ、しかし確かに溶かしていくのでした。

二つの誠実さが交差する時―魂の叫びと、涙の和解
自分のすべきことを見つけた昴。同じ頃、凛太郎もまた、二人の仲を裂いてしまった責任を感じ、昴に話をするために公園を訪れます。そこで彼は、自分のためではなく、ただひたすらに「和栗さんが大切にしている人を無視するのは俺にはできない」と、昴に深く頭を下げるのです。そのあまりにも誠実な姿に、昴の心の壁は完全に崩壊。「自分のことなんか、大嫌い…!薫子のこと、大好きなのに…っ!」。魂の叫びと共に、彼女は本当の気持ちを解き放ちます。二つの誠実さが交差した時、涙の向こうに、確かな和解の光が見えた瞬間でした。
心の深淵を読み解く~第6話 徹底解説
この「神回」には、キャラクターの心の機微、それを伝える巧みな演出、そして私たちの心を掴んで離さない深いテーマが散りばめられています。心の深淵のポイントを中心に、徹底的に解説していきましょう。
👇「薫る花は凛と咲く」の物語の概要です。
敵意からシンパシーへ―凛太郎に“同じ光”を見た昴の心境変化
「ああ、私は最低だ」。この昴の独白は、彼女の心の中で凛太郎という存在が、単なる「敵」から「自分を映す鏡」へと変わった瞬間を示しています。
当初、昴にとって凛太郎は、大切な薫子に近づく「千鳥の不良」であり、排除すべき異物でした。しかし、凛太郎は彼女の「会わないでほしい」という無茶な要求を、ただ拒否するだけでなく、その裏にある薫子への想いを汲み取り、真摯に向き合ってくれた。そして、そのことを薫子に告げ口することもなく、一人で抱えていた。
この「凛太郎の誠実さ」に触れた時、昴は気づいたはずです。彼もまた、自分と同じように、ただひたすらに薫子を大切に想い、守ろうとしている存在なのだと。

しかし、その気づきは安堵と同時に、強烈な自己嫌悪をもたらします。なぜなら、凛太郎は正々堂々と薫子に向き合っているのに、自分は親友を想うあまりに卑怯な手段を取り、その事実を隠そうとしてしまったからです。凛太郎の誠実さが眩しければ眩しいほど、自分のずるさが際立って見えてしまう。
ここに、敵意がシンパシーへと変わる瞬間の、痛みを伴うパラドックスがあります。自分と同じ「薫子を守りたい」という光を持つ凛太朗という存在に出会えた喜び。しかし、その光が自分の影を色濃く照らし出す苦しみ。この相反する感情こそが、昴の心をがんじがらめにしていた「黒い錆」の正体であり、彼女の凛太郎への感情が、単純な敵意から、尊敬と嫉妬と共感が入り混じった、極めて複雑なものへと変化した証なのです。

友情か、それ以上か―『光が死んだ夏』と対比する少女たちの特別な絆
昴の薫子に対する感情は、単なる「友情」という言葉では片付けられない、強い思慕を感じさせます。それはしばしば「百合的」と表現されますが、その関係性の本質を理解するために、ここで少し違う角度から光を当ててみましょう。例えば、近年話題を呼んだ『光が死んだ夏』で描かれる、よしきとヒカルの「ブロマンス」との比較です。
『光が死んだ夏』の二人の関係は、ヒカルという存在が「人ならざるもの」に変質してしまったという「秘密の共有」を核にしています。そこには、異質化した親友をそれでも受け入れようとする依存と、離れられない共犯関係のような、少し歪で危うい緊張感が常に漂っています。
一方、『薫る花』における昴と薫子の関係性は、もっと「光と影」のアナロジーで説明できます。幼い頃から、薫子は昴にとっての「ヒーロー」であり、太陽のような絶対的な光でした。強くて、優しくて、正しい。昴はその光に焦がれる一方で、自分はその光に照らされるだけの、弱くて臆病な影の存在だと感じています。彼女の薫子への想いは、恋愛感情というよりも、「信仰にも似た憧憬」と、「その光に釣り合う存在になりたい」という切実な願いに近いのです。
ブロマンスが「横並びの共犯関係」だとすれば、昴の感情は「見上げる先の絶対的な存在への思慕」。だからこそ、その「光」である薫子の隣に、自分ではない凛太郎という別の存在が立った時、彼女は激しい嫉妬と焦燥に駆られたのです。それは恋敵というよりも、自分の「聖域」が侵されたかのような感覚だったのではないでしょうか。この第6話は、そんな彼女が「見上げる」関係から、薫子の隣に立つ「対等な友人」になるための、魂の成長物語でもあったのです。

「私が大嫌い」―昴が求める“真の強さ”と自己否定の正体
「私は心から私が大嫌い」。この痛切な叫びの根底にあるのは、彼女が追い求める「真の強さ」と、それを持たない自分への絶望です。

では、昴が考える「真の強さ」とは何でしょうか。それは、冒頭の回想シーンに登場する幼い薫子の姿に集約されています。うんていから落ちても泣かず、他人の痛みに寄り添える優しさを持つ。誰が何と言おうと、自分の価値観で物事を判断できる。つまり、他者の評価や外部の環境に揺らぐことのない、確固たる「自己」を持つこと。それが、昴の憧れる「強さ」です。
彼女は、その強さを手に入れたくて、薫子を真似て髪を伸ばし、外見を取り繕ってきました。しかし、内面は幼い頃から何も変わっていないと感じています。
- 薫子を守りたいという想いが暴走し、嫉妬から凛太郎に卑怯な要求をしてしまう「弱さ」。
- そのことを薫子に責められなかったことに、心の底で安堵してしまう「ずるさ」。
- 薫子の隣に立つ凛太郎の誠実さを認められず、目を背けようとしていた「臆病さ」。
これら全てが、彼女の理想とする「真の強さ」とはかけ離れた自分自身の姿でした。「大嫌い」という言葉は、そんな理想と現実のギャップに苦しむ、彼女の魂からの悲鳴だったのです。彼女に足りなかったのは、腕力や気の強さではありません。自分の弱さやずるさを認め、それでも前を向こうとする「誠実さ」だったのかもしれません。そして、その「誠実さ」を、彼女は皮肉にも、敵視していた凛太郎の姿の中に見出すことになるのです。
「私が見てきた昴を信じる」―薫子の愛が自己肯定感の低い相手を救う理由
「私ね、自分が見てきたものを信じたいの。だから私は私が見てきた昴を信じる」。
この薫子のセリフは、本作のテーマを貫く、彼女の行動哲学そのものです。彼女はなぜ、自己肯定感の低い相手(今回は昴、そしてこれまでの凛太郎)に対して、これほどまでに強く、そして優しくいられるのでしょうか。
その理由は、彼女の生い立ちにヒントがあるのかもしれません。お嬢様学校「桔梗」に特待生として通う彼女は、もしかしたら私たちが見ている以上に、「家柄」や「成績」といった表面的なレッテルで判断される世界で生きてきたのかもしれません。あるいは、大切な誰かがそうした偏見に苦しむ姿を、間近で見てきた経験があるのかもしれません。
だからこそ、薫子は「一次情報」、つまり「自分が直接見聞きし、感じたこと」だけを判断の基準にしているのではないでしょうか。「千鳥の生徒だから」という噂ではなく、「自分が大好きなケーキを一緒に食べてくれた」「自分のために身を挺してくれた」という事実だけが、彼女にとっての凛太郎でした。
同じように、今回の昴に対しても、「親友を裏切るような行動をした」という結果だけを見るのではなく、「その根底には、昔から変わらない私のための優しさがある」という「自分が見てきた昴」の真実を信じ抜いたのです。
自己肯定感の低い人は、しばしば「どうせ自分なんて」と、自ら作り出した色眼鏡で世界を見てしまいます。薫子のやり方は、その色眼鏡を無理やり外させることではありません。ただひたすらに「私はあなたの素敵なところを、こんなにたくさん知っているよ」と伝え続ける。そのまっすぐな光を浴び続けることで、相手は自ら色眼鏡を外す勇気を得るのです。
彼女の「好み」は、おそらく「完璧な人」ではないのでしょう。不器用でも、間違えても、その根っこに「誠実さ」や「優しさ」を持っている人。そんな人の本質を見抜き、信じ、応援することに、彼女は喜びを感じるのではないでしょうか。その太陽のような愛こそが、凛太郎や昴のような、日陰でうずくまる心に光を届けるのです。
言葉にならない想い―「好き?」が“文字”で描かれた秀逸な演出
物語のクライマックス、昴が薫子に凛太郎への想いを問うシーン。
「薫子、もう一つ聞いていい?」というセリフの後、「紬くんのこと好き?」という問いかけは、音声ではなく、画面上のテキスト(文字)で表現されました。

これは、あまりにも秀逸な演出です。なぜ、あえてセリフにしなかったのか。
もしこの問いが音声(セリフ)で発せられていたら、それはどうしても「問い詰め」や「詮索」といったニュアンスを帯びてしまいます。昴が薫子の恋愛事情に踏み込む、という少し生々しい行為に見えたかもしれません。
しかし、これを「文字」で表現することで、この問いは昴の「心の声」、あるいは二人の間に流れる「空気」そのものへと昇華されます。それは、言葉にするにはあまりにもデリケートで、大切な問いかけでした。制作陣は、この瞬間の静寂と緊張感、そして互いを思いやる繊細な心の動きを、音声という情報を削ぎ落とすことで、逆説的に強調してみせたのです。

この演出により、私たちはキャラクターの声色に惑わされることなく、抱きしめ合う二人の表情、特に、問いかけられて少し驚き、そして愛おしそうに微笑む薫子の微細な表情の変化に、全神経を集中させることができます。言葉にならない、けれど確かにそこにある想いの交歓。アニメーションだからこそ可能な、詩的で、見事な心理描写でした。
映像が語る魂の解放―“黒い影”を打ち破る、神がかった心象風景の演出
昴の「胸を張ってあなたの隣を歩けるように」という決意の独白。このシーンで描かれた心象風景の演出は、まさに「神がかり」としか言いようがありません。この数分間に、彼女の魂の解放の全てが凝縮されています。
心の靄(もや)が晴れた昴の脳裏に広がるのは、象徴的なイメージの連続でした。
まず、彼女をがんじがらめにしていた「黒い影(錆)」。これは言うまでもなく、彼女の自己嫌悪や罪悪感のメタファーです。その中心で、幼い頃の薫子が現在の昴を抱きしめます。これは、彼女の苦しみの根源にあったのが、薫子への純粋な愛情であったことの再確認です。
そして、幼い自分が指さした先に、現在の薫子の後ろ姿が見える。昴は立ち上がり、薫子を追いかけます。この「立ち上がる」瞬間に、足元から砂煙のように舞い上がり、蹴散らされていく黒い影。これは、過去の自分、弱い自分との決別を意味します。

圧巻なのはその後のシーンです。薫子の隣に追いつき、並んで歩き始めた二人の姿を、カメラは上空から捉えます。そこには幼い二人の姿が。そして、幼い薫子が右腕を突き出し、拳を振りかざすたびに、画面に舞う黒い影の残滓が次々と打ち消されていくのです。

まるで、薫子が昴の心の中の迷いを、その「ヒーロー」の力で打ち払ってくれているかのよう。これは、昴が一人で戦っているのではなく、薫子の存在そのものが、彼女の弱さを打ち破る力になっていることを示す、感動的な演出です。
最後に登場する二輪の花。ピンクとブルーの花はおそらくアネモネでしょう。ピンクのアネモネの花言葉は「希望」「期待」。そして、青(紫)のアネモネの花言葉は「あなたを信じて待つ」。まさに、希望を胸に未来へ歩き出す昴と、そんな彼女を信じ続けてきた薫子の関係性そのものを象徴しています。

この一連のシークエンスは、単なる説明ではありません。映像、音楽、そして独白が一体となって、一人の少女の心が解放され、再生していく様を描ききった、アニメ史に残る名シーンと言えるでしょう。

「ホント、バカだわ私。」―底抜けの優しさに触れた昴の安堵と自嘲
凛太郎に頭を下げられ、彼の口から「保科さんは和栗さんが大切なんでしょ」「尊敬した」「優しい人だなって思った」という、予想だにしなかった言葉を聞いた昴。

彼女は、凛太郎を誤解し、敵視し、酷いことを言った自分を恥じます。そして、そんな自分の心配など杞憂に過ぎなかったとばかりに、どこまでも誠実な彼を目の当たりにして、思わず笑みがこぼれます。
「ホント、バカだわ私。」
このセリフに込められているのは、凛太郎への侮蔑では決してありません。これは、自分自身の愚かさに対する、愛おしさすら含んだ自嘲です。あんなに警戒し、思い悩んでいた自分が馬鹿みたいだ、という安堵の笑み。

同時に、この言葉にはもう一つの意味が隠されています。それは、「こんな底抜けのお人よしで、優しい人を好きになった薫子は、やっぱり間違っていなかった」という、親友の選択への確信と祝福です。自分の人を見る目がなかったことへの自嘲と、親友の人を見る目の確かさへの喜び。この二つの感情が入り混じった、非常に深く、温かい「バカだわ」なのです。

この瞬間、昴は凛太郎を「薫子の隣に立つにふさわしい人間」として、心から認めたのでしょう。公園にいた三羽の鳩が、白い鳩(薫子)を先頭に一緒に飛び立っていくシーンは、三人の関係が新たなステージへ向かって、共に飛び立ったことを象徴しているように見えました。制服の色を思わせる鳩たちが、序列なく、ただ一つの方向に未来へ向かっていく。それは、千鳥も桔梗も関係なく、三人が個人として繋がり、新しい物語を紡ぎ始めた、美しい門出のシーンだったのです。
総括:『薫る花は凛と咲く』が、疲れた心に灯す温かい光
怒涛の展開と、魂を揺さぶる感動に満ちた第6話。この物語が私たちに残してくれたものは何だったのでしょうか。最後に、この「神回」が持つ本当の意味と、これからの物語が私たちに見せてくれるであろう景色について、想いを馳せたいと思います。

タイトルの本当の意味―「大嫌い」の先にある、自分自身への「大好き」
今回のタイトル「大嫌い 大好き」。
物語を見終えた今、この言葉が持つ本当の意味が、深く心に染み渡ります。当初、これは他者への感情、例えば昴から凛太郎への「大嫌い」と、薫子への「大好き」だと思われました。しかし、物語が明らかにしたのは、もっと深く、もっと普遍的なテーマでした。
英語のタイトルでは「Self-Loathing, I Love You。そう、この物語の核心は「自己嫌悪(大嫌い)」と、それでも誰かを「愛する気持ち(大好き)」の葛藤だったのです。
昴は、理想の自分になれない弱い自分が「大嫌い」でした。しかし、そんな彼女を、薫子は「大好き」だと言ってくれた。凛太郎は、そんな彼女の優しさを「尊敬する」と言ってくれた。二人のまっすぐな光を受けて、昴は初めて、大嫌いな自分自身を、ほんの少しだけ許すことができたのかもしれません。
「いつか私もあなたが大好きだと言ってくれた私を、愛せるようになりたい」
この昴の最後の独白こそ、この物語の到達点です。これは、他者に認められることで完結する物語ではありません。他者の愛を力に変えて、自分自身を愛せるようになるまで歩み続ける、という自己受容への旅路の始まりを描いた物語なのです。
仕事で失敗して落ち込んだり、誰かの何気ない一言に傷ついたりして、「ああ、今日の自分は嫌いだ」と思ってしまう夜。きっと誰にでもありますよね。そんな夜に、この物語はそっと寄り添ってくれます。「大嫌い」な自分も、あなたの一部。そして、そんなあなたを「大好き」だと言ってくれる誰かがいるかもしれない。そしていつか、あなた自身が、自分のことを「大好き」だと言える日が来るかもしれない。この物語は、そんな温かい希望の光を、私たちの心に灯してくれるのです。
三角関係から生まれる新たなハーモニー
恋愛物語において「三角関係」は、しばしば嫉妬や対立、誰かが傷つく展開の起爆剤として描かれます。しかし、『薫る花』が示したのは、全く新しい三角関係の形でした。
凛太郎、薫子、昴。
この三人の関係は、恋の矢印が交錯する緊張関係ではありません。むしろ、互いの誠実さに触発され、互いを高め合い、三人で一つの美しいハーモニーを奏で始めた、そんな印象を受けます。
- 凛太郎は、昴の薫子を想う優しさに「尊敬」を抱きました。
- 昴は、凛太郎の薫子を想う誠実さに「信頼」を寄せました。
- そして薫子は、そんな二人の本質を、最初からずっと「信じ」続けていました。
誰かが誰かを蹴落とすのではなく、全員が全員の幸せを願う。この圧倒的な「優しさの連鎖」こそが、本作の真骨頂であり、私たちがこの物語にどうしようもなく惹きつけられる理由なのでしょう。それは、競争やマウンティングが溢れる現実世界で生きる私たちにとって、あまりにも眩しく、そして心の渇きを潤してくれる清らかな泉のような関係性なのです。
次回への期待―雨上がりの空に、どんな虹がかかるのか
さて、この歴史的な神回を経て、物語はどこへ向かうのでしょうか。
自己嫌悪の殻を破り、本当の強さへの一歩を踏み出した昴。彼女はもう、凛太郎と薫子の関係を脅かす存在ではありません。むしろ、二人の関係を誰よりも理解し、応援する、最強の味方となったはずです。
昴という心強い理解者を得たことで、凛太郎と薫子の関係も、また新たなステージへと進むでしょう。これまでは、二人の間に立ちはだかる「壁」に焦点が当たりがちでしたが、これからは、その壁をどう乗り越えていくか、という具体的な行動が描かれていくはずです。
そして忘れてはならないのが、凛太郎を支える千鳥の友人たちです。彼らとの友情もまた、この物語の重要な柱。凛太郎が薫子との関係を通して成長していく姿は、彼らにもきっと良い影響を与えていくに違いありません。
一つの大きな雨が止み、澄み渡った空が広がったような第6話。この雨上がりの空に、これからどんな美しい虹がかかるのか。三人の、そして彼らを取り巻く人々の未来が、楽しみで仕方がありません。
作品関連情報
2025年7月の放送開始以来、大きな反響を呼んでいる『薫る花は凛と咲く』。ここでは、放送・配信情報から、現在開催中および開催予定のイベント、最新グッズ情報までをまとめてお届けします。お見逃しのないよう、しっかりとチェックしてください。
放送・配信情報
テレビ放送
2025年7月5日より、TOKYO MXほか各局にて好評放送中です。
- TOKYO MX、BS11、とちぎテレビ、群馬テレビ: 毎週土曜 24:30~
- MBS: 毎週土曜 26:08~
※放送日時は変更になる可能性があります。最新の情報は公式サイトの発表をご確認ください。
インターネット配信
Netflixにて、毎週土曜25:00より地上波先行配信が行われています。また、ABEMAでは最新話の無料放送や、過去話の一挙配信なども実施されています。その他、各種動画配信サービスでも視聴可能です。
👇動画配信についてはこちらを参考にしてください。
イベント・コラボ情報
アニメ放送を記念し、作品の世界に浸れるイベントが続々と開催されています。
- コラボカフェ in 池袋: 2025年8月12日から8月24日まで、池袋の「eeo Cafe」にてコラボカフェが開催されました。お菓子作りがテーマの可愛らしい描き下ろしイラストを使用した限定グッズや、特典コースターが登場し、多くのファンで賑わいました。
- ポップアップストア in 吉祥寺: 2025年8月29日から9月7日まで、吉祥寺PARCOにてポップアップストアが開催されます。こちらでは、夏らしい浴衣姿のキャラクターたちが描き下ろしイラストで登場。アクリルスタンドや巾着といった限定グッズが販売されるほか、購入特典としてオリジナルポストカードが配布されます。
- スペシャルイベント: Blu-ray & DVDの発売を記念したスペシャルイベントが、2025年11月1日にイイノホール(東京・千代田区)にて開催決定。メインキャストが登壇する貴重な機会となります。
グッズ・書籍情報
作品の世界をより深く楽しむためのアイテムも多数展開中です。
- Blu-ray & DVD: アニメ第1巻が2025年8月27日に発売されます。店舗共通の第1巻購入特典として、原作者・三香見サカ先生描き下ろしの原作イラストを使用したA4縦型色紙が付属します。
- 原作コミックス: 2025年8月7日に最新刊となる第18巻が発売されました。全国の対象書店では、三香見サカ先生描き下ろしのイラストカードが購入特典として配布されています。なお、続く第19巻は2025年9月9日に発売が予定されています。
- オンラインくじ・グッズ: 「レトロ」をテーマにした新規描き下ろしイラストのオンラインくじが、2025年8月14日から9月11日までの期間限定で販売されています。また、前述のコラボカフェやポップアップストアでも、イベントでしか手に入らないオリジナルグッズが多数ラインナップされています。
最後までお読みいただき、本当にありがとうございました。
少しだけ筆が止まっていたこの作品の感想ですが、第6話が与えてくれた衝撃と感動は、私に再びキーボードを叩く力をくれました。それはきっと、物語の中でキャラクターたちが、互いを信じ、支え合い、一歩を踏み出す勇気を見せてくれたからだと思います。
忙しい毎日の中で、ふと心が立ち止まってしまいそうになった時。
誰かと自分を比べて、少しだけ自信を失ってしまった時。
どうか、この物語と、この場所のことを思い出してください。
あなたの心に、あのケーキ屋さんのような、ささやかで温かい甘さを届けられる。そんなブログであり続けたいと、心から願っています。
それでは、また次の物語でお会いしましょう。
☆☆☆☆☆今回はここまで。
👉使用した画像および一部の記述はアニメ公式サイトから転用しました。
【アニメ関連はこっちから】
びわおちゃんブログをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。