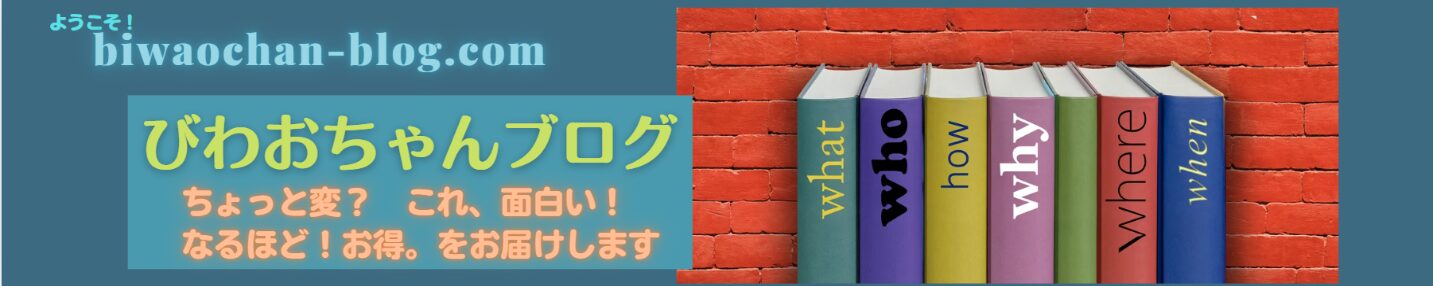こんにちは!びわおちゃんブログ&アニオタWorld!へようこそ。
忙しい毎日の中で、ふと心が渇いていると感じることはありませんか? 理屈ではなく、魂を揺さぶられるような物語に触れたい。涙で心を洗い流したい。そんな夜に、ふと思い出す映画があります。それが、『君の膵臓をたべたい』です。
2017年に公開された実写映画は社会現象ともいえる大ヒットを記録し、多くの人の心に忘れられない感動を刻み込みました。浜辺美波さんと北村匠海さんが織りなす、あまりにも切なく、あまりにも美しい二人の時間は、今も鮮やかに記憶に残っているのではないでしょうか。
しかし、その翌年に、もう一つの『キミスイ』がひっそりと、しかし確かな輝きを放って公開されたことをご存知でしょうか。それが、劇場アニメ版『君の膵臓をたべたい』です。
「実写版が素晴らしかったから、アニメ版は観なくてもいいかな…」
「興行的には実写版ほどではなかったみたいだし、どうなんだろう?」
もしあなたがそう思っているのなら、それはあまりにも勿体ないことかもしれません。アニメ版は、実写版とは全く異なるアプローチで、しかし同じくらい深く、原作の持つ魂に迫った「もう一つの傑作」なのです。
この記事では、アニメ映画版『君の膵臓をたべたい』を主軸に、実写版の感動を振り返りながら、二つの作品がそれぞれ目指した場所、そしてアニメだからこそ到達できた表現の極致について、じっくりと掘り下げていきたいと思います。二つの『キミスイ』を知ることで、あなたの心の中にある感動は、きっと2倍、3倍にも深まっていくはずです。
作品紹介 – 原作小説『君の膵臓をたべたい』が放つ普遍的な輝き

すべての始まりは、2015年に刊行された一冊の小説でした。当時、まだ無名の新人作家であった住野よる氏が放ったデビュー作、『君の膵臓をたべたい』。一度聞いたら忘れられない、少しぎょっとするようなタイトル。しかし、そのページをめくった読者は、タイトルとのギャップに衝撃を受け、そして温かい涙を流しました。
物語は、高校生の「僕」が病院の待合室で一冊の文庫本を拾うところから始まります。その本のタイトルは「共病文庫」。持ち主は、クラスの人気者で、太陽のような笑顔を振りまく少女・山内桜良。そこに綴られていたのは、彼女が膵臓の重い病を患い、余命いくばくもないという、誰にも明かしていない秘密でした。
クラスで唯一、彼女の秘密を知ってしまった「僕」。自ら人との関わりを絶ち、静かに本を読むことだけが世界のすべてだった彼の日常は、桜良の「死ぬ前にやりたいこと」に付き合わされることで、音を立てて変わり始めます。正反対の二人が、秘密を共有することで過ごす、限られた時間。それは、やがて二人の関係を、友情でも恋愛でもない、もっと特別な、魂の結びつきへと変えていきます。
👇こんな「けしからん!」作品もあるんですね(笑)
この物語がなぜ、これほどまでに多くの人々の心を掴んだのでしょうか。それは、若い二人の切ない恋愛物語という枠を超え、「人が生きることの意味」「他者と関わることの尊さ」「一日一日を大切に生きることの価値」といった、私たちが人生で誰もが向き合う、普遍的で根源的なテーマを、真正面から描いているからに他なりません。 桜良の言葉、そして「僕」の変化を通して、私たちは自分自身の生き方をも、静かに問われることになるのです。
実写版の記憶―スクリーンに刻まれた二人の「生」と「死」
原作の感動が日本中を席巻する中、2017年に公開された実写映画版は、その熱狂をさらに大きなものへと押し上げました。原作の持つテーマ性を損なうことなく、映画というメディアでしか表現できない感動を創り出したこの作品は、今なお多くの人にとって「最高の『キミスイ』」として記憶されています。その成功の要因は、何と言っても主演二人の圧倒的な存在感と、原作にはない大胆なオリジナル要素にありました。
浜辺美波と北村匠海が起こした化学反応
浜辺美波が体現した「桜良」という生命力
この映画を観た誰もが、息をのんだはずです。スクリーンの中で、浜辺美波が「山内桜良」として、ただ存在しているのではなく、確かに「生きて」いることに。

彼女が演じた桜良は、単に明るく元気なヒロインではありませんでした。死という絶対的な恐怖を腹の底に飼い慣らし、だからこそ「今」この一瞬を、燃え尽きる寸前の蝋燭のように、誰よりも強く輝かせようとする。その刹那的な煌めきと、まぶしい笑顔の裏側に張り付いた、ナイフのように鋭い孤独の影。浜辺美波は、その二面性を見事に、そして生々しく体現していました。

特に観る者の胸を打ったのは、彼女の「泣きそうで、決して泣かない」演技です。病の辛さ、未来がないことへの絶望を悟られまいと必死に笑顔を作る、その仮面がほんの一瞬、ミリ単位で剥がれそうになる。でも、決して剥がれない。観ているこちらの胸が張り裂けそうになるのに、彼女はスクリーンの中で涙腺を締め、また笑う。この神業のような感情のコントロールが、桜良というキャラクターに、フィクションを超えた圧倒的な生命力を与えました。原作を読んだ時に私の頭の中にいた桜良は、この映画を観た後、完全に浜辺美波の桜良に上書きされていました。それは、彼女が私の貧弱な想像力を遥かに超える「生きた桜良」を、そこに現出させたからに他なりません。
北村匠海が表現した「僕」の静かな変容
浜辺美波というあまりにも強烈な太陽の光を全身に浴びながら、決して消し飛ぶことなく、静かに、しかし確実にその形を変えていく「影」。それが、「僕」を演じた北村匠海の功績です。

感情を表に出さず、人間関係をノイズとして処理してきた少年が、桜良という予測不能な生命体に振り回される中で、徐々に人間性を取り戻していく。その心の機微を、北村匠海は視線の動きや、ほんのわずかな口元の歪みだけで、驚くほど繊細に表現しました。彼の演技があったからこそ、桜良の輝きはより一層際立ち、二人の関係性の変化に、観客は深く感情移入することができたのです。

そして、物語のクライマックス。桜良の死後、「共病文庫」を読み、感情を爆発させるあの慟哭のシーン。声を押し殺し、床に崩れ落ちるあの嗚咽は、単なる悲しみではありません。後悔、感謝、愛情、そして彼女の想いを引き継いで生きるという決意。その全てがごちゃ混ぜになった魂の叫びでした。浜辺美波という「事件」と、その光を受け止め、自らもまた静かに発光する北村匠海の存在。この二つの才能が起こした奇跡的な化学反応こそが、実写版『キミスイ』を不朽の名作たらしめたのです。
原作にはない「12年後」という発明
実写版が原作ファンからも高く評価されたもう一つの理由は、大胆でありながら、物語のテーマをより深く掘り下げげることに成功した、秀逸なオリジナル要素にあります。それが、**「12年後の現代パート」**の追加です。

原作は、高校時代の「僕」の視点のみで物語が進行します。しかし実写版では、12年の時を経て母校の教師となった「僕」(演:小栗旬)と、結婚を控えた桜良の親友・恭子(演:北川景子)の視点が加えられました。この改変に対しては、「蛇足だ」という批判的な意見も一部には存在します。しかし、私はこの「発明」が、映画というメディアで物語を語る上で、最良の選択の一つだったと考えています。
なぜなら、この現代パートが加わったことで、物語は単なる痛々しい青春の回想録ではなくなったからです。桜良の死が、遺された人々のその後の人生に、どれほど深く、そして温かい影響を与え続けたのか。彼女との出会いがなければ、決して教師になっていなかったであろう「僕」。彼女の遺志を継ぎ、親友の想いを胸に生きてきた恭子。彼らの姿を通して、私たちは、桜良の短い人生が決して無駄ではなかったこと、彼女の魂が確かに受け継がれていることを知るのです。

桜良の死という悲劇的な結末に打ちのめされた観客に、確かな「救い」と未来への希望を与えてくれる。この「12年後」という発明は、原作のテーマを損なうどころか、むしろ映画という形で物語を昇華させ、より多くの人々の心に届けるための、見事な脚色だったと言えるでしょう。
もう一つの傑作―アニメ映画版が描いた「原作の魂」
実写版が打ち立てた金字塔。その翌年に公開されたアニメ映画版は、興行的には及ばなかったものの、観た人の心に静かで深い感動を残す、まさに「もう一つの傑作」と呼ぶにふさわしい作品でした。 実写版が大胆な「発明」で物語を再構築したのに対し、アニメ版が目指したのは、どこまでも原作に寄り添い、その魂を忠実に映像化するという「誠実さ」でした。
魂を吹き込んだ声優陣―高杉真宙とLynnの挑戦
アニメ版の魅力を語る上で欠かせないのが、主人公「僕」とヒロイン・山内桜良の声を担当した二人のキャスト、高杉真宙さんとLynnさんの存在です。このキャスティングは、声優初挑戦の若手俳優と、実力派のプロ声優という、興味深い組み合わせでした。
「僕」役:高杉真宙―初挑戦のプレッシャーと誠実な役作り

当時、若手俳優として活躍していた高杉真宙さん。アニメ好きを公言していた彼にとって、本作は念願の声優初挑戦の場でした。しかし、それは同時にとてつもないプレッシャーとの戦いでもありました。実写で高い評価を得ている作品であること、そして何より「声100%の世界」で感情を表現することの難しさに、彼はひたすら緊張していたと語っています。
製作プロデューサーは、物語を通して成長していく「僕」を表現するために、「上手さと未完成さを兼ね備えた」声の芝居を求めていました。まさにその時、偶然目にした高杉さんのナレーションを聞き、「“僕”の声を見つけた」と確信したそうです。彼のキャスティングは、キャラクターの持つ繊細さを表現するための、運命的な出会いでした。
彼の演技は、一部では「棒読みに聞こえる」という意見もありましたが、それは人と関わるのが苦手な「僕」の、感情を表に出さないキャラクター性を見事に表現した結果とも言えます。高杉さんの落ち着いた声音と繊細な演技は、「僕」というキャラクターにこれ以上ないほどの説得力を与えていたのです。そして物語のクライマックス、感情を爆発させるシーンでは、その抑制された演技とのコントラストが、観る者の心を激しく揺さぶります。彼自身、共演者の演技に感動し、素で泣きそうになったと語っており、初挑戦ながら全身全霊で役に向き合ったことが伺えます。
「桜良」役:Lynn―物語の魂を支えた圧巻の演技力

そんな高杉さんの挑戦を支え、作品の感動を決定づけたのが、ヒロイン・桜良を演じたプロの声優・Lynnさんです。劇場アニメのメインヒロインを演じるのは本作が初めてだったという彼女ですが、その演技は圧巻の一言でした。
Lynnさんは、実写映画を観たタイミングでオーディションの話を受け、「何が何でも演じたい」という強い思いで役に臨んだと語っています。その気迫は、スクリーンの中の桜良に、鮮烈な命として宿りました。天真爛漫な明るさの裏に隠された病への恐怖と、それでも「今」を全力で生きようとする切実な願い。その複雑な感情の機微を、常に口角を上げながら話すなどの技術も駆使し、声色と息遣いだけで完璧に表現しきっていました。
彼女の演技の凄みは、共演した高杉さんの言葉からも伝わってきます。高杉さんは、Lynnさん演じる桜良のセリフを素直に聞いただけで、自然に感情を引き出してもらったと感謝を述べているのです。
声優初挑戦で緊張する高杉さんの「未完成さ」と、それを真正面から受け止め、物語の感情の核を支えたLynnさんの「熟練」。この二人の化学反応こそが、アニメ版『キミスイ』に、実写版とは違う、どこまでも純粋で心に響く感動をもたらしたのです。

比較でわかる、アニメ版と実写版の目指した場所
同じ原作から生まれながら、なぜ二つの作品はこれほどまでに違う手触りの感動を与えるのでしょうか。それは、それぞれのメディアの特性を最大限に活かし、目指したゴールが異なっていたからです。
| 比較項目 | 実写映画版(2017) | アニメ映画版(2018) |
|---|---|---|
| 物語の構成 | 過去と12年後の現代パートが交差する「発明」的構成 | 原作に忠実な、過去の時間軸のみで描く「誠実」な構成 |
| 最大の魅力 | 俳優陣の生身の演技がもたらす圧倒的なリアリティと生命力 | アニメならではの詩的な映像美と、純度の高い心理描写 |
| 主人公の成長 | ヒロイン亡き後、12年を経て手紙をきっかけに再生を果たす | ヒロインと過ごす中でリアルタイムに変化していく心の機微が描かれる |
| ヒロイン像 | 浜辺美波が体現する、生命力と儚さが同居した「生きた桜良」 | Lynnが演じる、内面的な繊細さや儚さが際立つ、透明感のある桜良 |
| 演出の方向性 | 観客に「救い」を与える、カタルシス重視のエンターテイメント | 原作の文学的な雰囲気を尊重し、登場人物の心情に深く寄り添う |
| 作品の手触り | 温かくも切ない、魂の救済の物語 | 儚くも美しい、ガラス細工のような青春の記録 |
この表からもわかるように、どちらが優れているかという話ではありません。実写版が桜良の死がもたらした「その後」までを描き、遺された人々の「救い」の物語として観客を感動の渦に巻き込んだのに対し、アニメ版はあくまで「僕」と桜良が過ごした、二度と戻らない「あの時間」そのものの輝きと儚さを、純度100%で描き切ることに注力したのです。
アニメならではの見どころ3選
では、具体的にアニメ版は、どのようなアプローチで『キミスイ』の世界を描いたのでしょうか。実写版を観た方にこそ注目してほしい、アニメならではの見どころを3つのポイントに絞ってご紹介します。
見どころ1: 原作の文学性を昇華させた「詩的な映像美」
アニメ版を観てまず心奪われるのは、その淡く、繊細で、どこか懐かしい映像美です。ポップとも美麗とも違う、素朴で落ち着いたトーンのビジュアル。しかし、これこそが『キミスイ』という物語を描く上で、最良の選択だったのです。

なぜなら、この物語のテーマは「何でもない日常の大切さ」だからです。アニメ版のビジュアルは、そのテーマと完璧に響き合っていました。
- 光と影の演出: 二人が心を通わせるシーンでは柔らかい光が差し込み、心がすれ違う場面では冷たい影が落ちる。特に、図書館のシーンでの木漏れ日や、夜の病院の廊下に落ちる光と影のコントラストは、言葉以上に二人の心情を物語ります。
- 桜の花びらのメタファー: 桜良の名前を象徴するかのように、物語の重要な局面で、大量の桜の花びらが舞い散ります。それは時に桜良の生命力の輝きのように、時に彼女の命が散っていく様を暗示するように、美しくも残酷なメタファーとして機能します。
- 花火のシーン: 原作でも重要な役割を果たす花火のシーンは、アニメーションならではの表現の独壇場です。夜空を彩る大輪の花火の光が、秘密を共有する二人の横顔を照らし出す。その一瞬の永遠のような美しさは、実写では表現しきれない、アニメならではの詩情に満ちています。
これらの演出は、原作小説が持つ文学的な雰囲気、行間に漂う声にならない感情を、色と光と動きで丁寧に掬い取り、私たちの心に直接届けてくれます。
見どころ2: 「僕」のモノローグが誘う、深い没入感
この物語は、ほとんどが「僕」のモノローグによって進行します。アニメ版では、高杉真宙さんが演じる「僕」の、抑揚の少ない、それでいて確かな感情の揺らぎを感じさせる声が、彼のキャラクター性を見事に表現しています。
実写版の北村匠海さんが見せる表情や仕草の演技も素晴らしいものでしたが、アニメ版では、「僕」の内面で渦巻く思考や感情が、モノローグとしてよりダイレクトに、純度の高い形で私たちの耳に届きます。桜良に振り回される戸惑い、彼女の言葉に心を動かされる瞬間、そして彼女を失うことへの言いようのない恐怖。「僕」の視点に深く没入し、彼の心の変化をリアルタイムで追体験できるのは、アニメ版ならではの大きな魅力です。

見どころ3: 「星の王子さま」が示す、二人の関係性のメタファー
アニメ版を観る上で、もう一つ知っておくと物語が何倍も深まる重要なモチーフがあります。それが、サン=テグジュペリの小説**『星の王子さま』**です。
作中で「僕」が愛読する本として登場する『星の王子さま』は、単なる小道具ではありません。物語全体が、『星の王子さま』のメタファーとして構築されているのです。
- 「僕」と王子さま: 人間関係を煩わしく思い、自分の小さな世界に閉じこもっている「僕」は、自分の星にたった一人で暮らす王子さまそのものです。
- 桜良と「大切な一輪のバラ」: 王子さまが、自分の星に咲いたたった一輪のワガママなバラを愛し、そのバラに振り回されるように、「僕」もまた、ワガママで気まぐれな桜良に振り回されながらも、彼女が自分にとって「他の誰とも違う、たった一人の特別な存在」であることに気づいていきます。
- 「関係を作る」ということ: 『星の王子さま』の中でキツネが王子さまに教える「なつく(=関係を作る)」ことの大切さは、『キミスイ』の根幹をなすテーマと完全に一致します。桜良は、まさに「僕」との「関係」を必死に作ろうとしたのです。
このメタファーを意識して観ると、桜良がなぜあれほど「僕」に執着したのか、そして「僕」がなぜ桜良に惹かれていったのか、その魂のレベルでの結びつきがより深く理解できます。原作のテーマを、別の文学作品を引用することで重層的に描き出すという、非常に知的で高度な演出であり、アニメ版の大きな見どころの一つと言えるでしょう。

これから観るあなたへ―感動を2倍にする鑑賞アドバイス
ここまで読んで、「実写版もアニメ版も、両方面白そう!」と思っていただけたら、とても嬉しいです。最後に、これから『キミスイ』の世界に触れるあなたへ、それぞれの作品をより深く味わうための、ささやかな鑑賞アドバイスをお贈りします。
まずは「実写版」から観るあなたへ
ポイント1: 二人の俳優の「魂の演技」に注目する
まずは何も考えず、浜辺美波さんと北村匠海さんの演技に身を委ねてみてください。特に、セリフのないシーンでの二人の表情や視線の交錯には、言葉以上の感情が溢れています。桜良がふと見せる寂しげな横顔、「僕」が彼女から目が離せなくなる瞬間。その一瞬一瞬に、二人の心の距離が変化していく様が刻まれています。
ポイント2: 「12年後」の物語がもたらす意味を考える
物語を観ながら、「なぜ、この12年後のシーンが挿入されているんだろう?」と考えてみてください。高校時代の切ない物語と、大人になった彼らの現在が交差する時、そこにどんな意味が生まれるのか。桜良の死が「悲しい終わり」ではなく、遺された人々の未来に繋がる「希望の始まり」であったことを感じられた時、この映画の本当の感動があなたを包み込むはずです。

ポイント3: 原作との「僕」のキャラクターの違いを楽しむ
もし原作を読んでいるなら、原作の「僕」の、より屈折した皮肉屋なキャラクターを思い浮かべながら観るのも一興です。映画版の北村匠海さんが演じる「僕」が、原作よりも少しナイーブで共感しやすいキャラクターとして描かれていること。その違いが、映画をより多くの人に届けるための、巧みなアレンジであることがわかるでしょう。
次に「アニメ版」を観るあなたへ
ポイント1: 心象風景を描く「光と色彩」に心を寄せる
アニメ版は、映像そのものがキャラクターの感情を代弁しています。二人が一緒にいる時に画面を満たす温かい光、心が離れる時の冷たい色彩。特に、ラストシーン近くで描かれる、満開の桜並木のシーンの映像美は圧巻です。その映像の一つ一つが、二人が過ごした時間の輝きと、失われたものの大きさを、私たちの心に深く刻みつけます。

ポイント2: キャストの「声の化学反応」を感じる
「僕」役の高杉真宙さんと、桜良役のLynnさん。声優初挑戦の俳優と、実力派のプロ声優という二人が、どのような化学反応を起こしているかに耳を澄ませてみてください。高杉さんの抑制された声が、Lynnさんの生命力溢れる声と出会うことで、どのように感情を帯びていくのか。その変化の過程こそが、アニメ版の感動の核心をなしているのです。
ポイント3: 『星の王子さま』のメタファーを読み解く
鑑賞前に、あるいは鑑賞後に、『星の王子さま』の物語を思い出してみてください。アニメ版では、桜良の遺書のシーンなどが『星の王子さま』の物語になぞらえて語られます。二人の関係が、なぜ友情でも恋愛でもなかったのか。なぜ桜良にとって「僕」が、他の誰とも違う唯一の存在だったのか。その答えが、このメタファーの中に隠されています。それを理解した時、二人の魂の結びつきの深さに、改めて涙することになるでしょう。

物語の扉を閉じて、あなたの心に残るものは何ですか?
実写版『君の膵臓をたべたい』は、桜良の死が遺された人々の人生をどう変えたかを描く、「救い」の物語でした。
そして、アニメ版『君の膵臓をたべたい』は、二人が生きた「限られた時間」そのものの輝きと儚さを、純粋な形で記録した、ガラス細工のような物語でした。

どちらか一方だけを観るのも素晴らしい体験です。しかし、両方の作品を観ることで、『君の膵臓をたべたい』という物語が持つ、多層的で深い感動の全体像が見えてくるはずです。
もしあなたが今、何気ない日常に少しだけ疲れていたり、心を揺さぶるような感動を求めていたりするのなら、この週末、ぜひ二つの『キミスイ』に触れてみてください。涙で心が洗い流された後、きっとあなたの世界は、昨日よりも少しだけ愛おしく、輝いて見えるはずですから。

VODでいつでもどこでも!
自分のペースでじっくり観たい方は、動画配信サービス(VOD)が便利です。U-NEXTとAmazonプライムで見ることができますよ。まだ加入していないよ!って方は下の徹底比較も参考にしてください。
☆☆☆☆☆今回はここまで。
👉使用した画像および一部の記述は映画.com,劇場アニメ公式サイトから転用しました。
【アニメ関連はこっちから】
びわおちゃんブログをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。