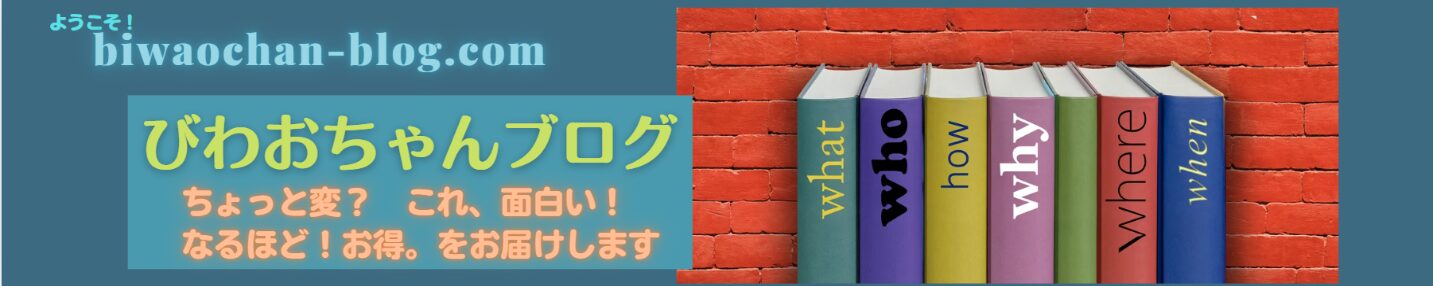はじめに:AI制作アニメ「ツインズひなひま」が投げかけた波紋
ちょっと前のアニメの話をします。2025年3月28日に放送されたアニメ「ツインズひなひま」です。
生成AIを活用して制作されたということで、放送前から一部で大きな話題を呼びましたね。 アニメ制作の新たな可能性を示す試みとして注目されましたが、残念ながら作品そのものの評価は芳しくなかったようです。「AIアニメ」という言葉だけが先行し、期待と不安が入り混じる中で世に出たこの作品。僕たちアニメファンにとって、それは一体何だったのでしょうか?
このブログでは、僕のアニオタとしての視点から、「ツインズひなひま」をAI制作という観点から深掘り考察していきます。制作側の意図、作品から感じられたAIの可能性と限界、そして何よりも、なぜ多くの視聴者が失望を感じたのか。時には厳しく、しかしアニメへの愛を持って語っていきたいと思います。
「ツインズひなひま」とはどんなアニメだったのか?
まずは、この作品がどんな物語だったのか、そして僕がどう感じたかをお伝えします。
あらすじ:女子高生TikTokerの非日常的な冒険…のはずが?
物語の主人公は、ひまりとひななという双子の女子高生TikToker。 バズる動画を作るために日々奮闘する彼女たちが、ある日奇妙な猫との出会いをきっかけに、見慣れた日常が異変をきたし、不思議な世界へと足を踏み入れていく…というのが大まかなあらすじです。
👇公式サイトのストーリー画像はこの1枚のみです。アニメファンを舐めてますね。

公式サイトのあらすじ情報もどこかフワッとしていて、正直なところ、これだけでは魅力が伝わりにくい印象を受けました。 「スペシャル」コンテンツもいまだに「coming soon…」のままですし(2025年5月現在)、こうした点からも、作品への力の入れ具合が垣間見えるような気がしてしまいます。

見どころポイント…という名のツッコミどころ満載の展開
さて、肝心の内容ですが…正直、見どころというよりはツッコミどころが満載だったと言わざるを得ません。
冒頭、スマホ画面越しの「ChikChik」撮影シーン。再生数を全く稼げないという「いまどきのJK」の生態を描写しているつもりなのかもしれませんが、僕にはどうもおじさんが想像で作ったJK像にしか見えず、滑稽に感じられました。生成AIという最先端技術を使いながら、描かれるJK像が古臭いというのは、なんとも皮肉なものです。このズレが制作陣の狙いだったとしたら…それはそれで高度なギャグですが、そうは思えませんでした。挙句の果てには妹のひなな(赤髪の方ですね)が雑草を食べる始末。この掴みの弱さ、開始1分30秒で「僕らは何を見せられてるんだ?」と疑問符が浮かぶ展開は、プロの仕事とは思えませんでした。

コーラと見せかけてお汁粉を買い、「これよ!」とドヤ顔するシーンも、「10年前のJKですか?」と問いかけたくなりました。ギャグをやりたいなら、もっと現代の作品を研究すべきです。この古臭いセンスは、作品全体の世界観にも通底していたように感じます。ストーリー制作をAIに任せたのかどうかは分かりませんが、もし人間の手によるものだとしたら、かなり昭和的な発想だなと思わざるを得ません。生成AIなら、プロンプト次第でもっと斬新なアイデアが出てきたのではないでしょうか。

AIは「ツインズひなひま」をどう描いたのか?僕の目に映ったAI活用の実態
「全編AIを活用したアニメとしては日本初の地上波テレビ放送」と謳われた本作。 その実態はどうだったのでしょうか。
公式サイトから透ける「本気度」の欠如
先にも触れましたが、公式サイトの情報量の少なさや更新の滞り具合は、作品に対する制作側の熱意を疑わせるには十分でした。 本当にお金と手間をかけて、良いものを作ろうという気概があったのでしょうか。この中途半端な印象は、残念ながら作品そのものにも通底していたように感じます。
制作陣のコンセプトと視聴者の期待の大きなズレ
制作側から見れば、生成AIの導入はコスト削減、納期短縮、制作スタッフの負担軽減、アニメーターの資源確保といったメリットがあったのかもしれません。 しかし、これらのメリットが必ずしも視聴者にとってプラスに働くとは限りません。むしろ、僕たちアニメファンは、作品に無限の夢と希望を託し、採算度外視とも思える手間と時間と情熱が注ぎ込まれた作品にこそ心惹かれるものです。
「ツインズひなひま」は、アニメ界の構造的な問題に一石を投じる意図があったのかもしれません。しかし、その試みが視聴者に支持されたかと言えば、SNSでの反応を見る限り疑問です。 「ツインズひなひま 炎上」や「ツインズひなひま 1話だけ」といった残念な検索ワードが出てくる現状が、その答えを物語っているのではないでしょうか。
AIらしさはどこに?チープさが際立った映像表現
猫が登場してから、ようやくAIが生成したと思われる動画が次々と出てきましたが、そのクオリティは正直言って期待外れでした。立体感のない平べったい動画、滑らかさのない動き。これがコスト削減の結果なのかもしれませんが、AIはプロンプト次第でいくらでも働き続けてくれるはずです(しかも人件費はかからない)。生成AIに作らせる部分でこそ、質の高いものを追求するべきではなかったのでしょうか。
唯一「AIらしい」と感じたのは、「並行世界」の風景でした。あの異常な感じと不自然さは、確かに現在の生成AI画像や動画に見られる特徴(指が6本あったり、関節が逆に曲がったり、色彩感覚が人間の美的感覚とズレていたり)をよく捉えていたと思います。しかし、それは褒め言葉ではありません。むしろ、監督や監修者がAIの出力を適切に修正するスキルや知見を持っていなかった、あるいはその手間を惜しんだ結果ではないかとすら思えてしまいます。

クリエイターインタビューでは、「今、本業は漫画家なので、アニメの話をするのは非常に不向きなんですよ。最近のアニメ事情も詳しく知らないしね。」と発言しています。このようなスタンスでは、良い作品が生まれるはずもありません。


「サポーティブAI」の理想と現実
本作はAIをクリエイターによる創作活動の補助ツールとして活用する「サポーティブAI」という考え方で制作されたとされています。 本編の95%以上のカットで生成AIを活用し、仕上げ段階で人間のアニメーターが加筆修正を行ったとのことです。 クリエイターの負担軽減や作業効率化の実証を兼ねるという目的もあったようです。
しかし、結果として生まれた作品がこれでは、「サポーティブAI」の可能性を十分に示せたとは言えないでしょう。むしろ、コストや期間を3分の2にできたとしても、その分クオリティが大きく犠牲になったのではないか、という印象です。
なぜ「ツインズひなひま」は期待を裏切ったのか?
この作品の残念な結果は、果たしてAI技術の限界だったのでしょうか?僕はそうは思いません。
問題はAI技術の未熟さではない!制作陣の「やる気」の問題
今の生成AIの限界でやれなかったことが失敗の要因なのではありません。最大の原因は、制作陣に「やる気」がなく、AIを使いこなせる熱意のあるスタッフを集められなかったことにあると断言したいです。スタッフのAIに対する理解不足や、安易な活用方法への「はき違え」が、この作品のクオリティを著しく下げたのではないでしょうか。
脚本についても、尺が足りていない、ストーリーが薄いといった指摘が多く見られました。 25分という短い尺で、しかも1話完結という構成では、深い物語を描くのは難しかったのかもしれません。 しかし、それならばなおさら、映像表現やキャラクターの魅力で視聴者を引き込む必要があったはずです。
「時間泥棒」と呼ばれても仕方ない作品だった
正直に言います。このアニメを見た後、僕は「貴重な時間を奪われた」と感じました。同じ「時間泥棒」なら、もっと心ときめく作品に時間を盗まれたかったです。例えば、以前僕がブログで熱く語った「リコリコショート」のような作品に。
これこそが「正しい」時間泥棒です!
【最終話】リコリコショート第6話「Brief respite」~感動の花の搭
この「ツインズひなひま」に費やした時間は、残念ながら僕にとって有意義なものとは言えませんでした。
「ツインズひなひま」がアニメ界に突きつけた課題と今後のAIアニメへの提言
実験作としての意義はあったのかもしれません。 しかし、この作品がAIアニメのイメージを悪くしてしまったとしたら、それは大きな損失です。
AIアニメ=低予算・駄作というイメージの定着?
「ツインズひなひま」の出来栄えは、視聴者に「AIアニメ=低予算でクオリティの低い作品」というネガティブなイメージを植え付けてしまった可能性があります。 かつて3DCGがアニメに導入され始めた頃も、そのぎこちなさから批判的な意見が多くありました。しかし、技術の進歩とクリエイターの努力によって、今では素晴らしい3DCGアニメが数多く生まれています。AIアニメも同様の道を辿る可能性はありますが、そのためには今回の失敗を真摯に受け止める必要があります。
AIはツールであり、熱意と才能あるクリエイターがいてこそ輝く
生成AIはあくまでツールです。どれだけ高性能なAIが登場しても、それを使う人間の熱意、才能、そして明確なビジョンがなければ、良い作品は生まれません。「ツインズひなひま」は、そのことを改めて浮き彫りにしたと言えるでしょう。AIを単なるコスト削減や効率化の道具としてしか見ていないのであれば、視聴者の心に響く作品を作ることは不可能です。
アニメファンが本当に見たいものとは何か
僕たちアニメファンが求めているのは、技術の目新しさだけではありません。心を揺さぶるストーリー、魅力的なキャラクター、そして作り手の情熱が込められた作品です。AIがその実現を助けるツールとなり得るのなら歓迎しますが、AIを使うこと自体が目的化してしまい、作品の本質的な魅力が損なわれるようなことがあってはなりません。
まとめ:実験作で終わらせるには惜しい?いや、やはりこれは…
「ツインズひなひま」は、AIアニメの黎明期におけるひとつの「事例」として記憶されるのかもしれません。しかし、それは決して輝かしい成功事例としてではなく、むしろ多くの課題を露呈した反面教師として語り継がれることになるでしょう。
一部には「実験作としてはあり」「惜しいところも多い」といった擁護の声もあるようですが、僕は厳しい評価を下さざるを得ません。この作品から感じられたのは、制作側の熱意の欠如と、AIという新しい技術に対する安易な姿勢でした。
今後のアニメ制作において、AIがどのように活用されていくのか注目していきたいと思いますが、今回の「ツインズひなひま」の轍を踏むことなく、真にアニメファンをワクワクさせるようなAI活用がなされることを心から願っています。そして何よりも、AIを使うにしても使わないにしても、作り手の方々には常に「面白いアニメを作りたい!」という純粋な情熱を持ち続けてほしい。それが、一アニメファンとしての切なる願いです。
配信情報
このショートムービーは、僕がいつも紹介している配信プラットフォームで見ることができます。
僕が紹介するアニメは以下のVODで見れるので加入してない人はどれかに加入するといいですよ。
| 配信サービス | 月額料金(税込) | 無料期間 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| U-NEXT | 2,189円 | 31日間 | 豊富なコンテンツ数。ラノベやマンガも楽しめ、利用料金の40%がポイント還元。 |
| Amazonプライム | 600円 | 30日間 | 独占配信や話題作が充実。Amazon利用者におすすめ。 |
| ABEMAプレミアム | 960円 | 2週間 | 地上波放送中の作品や恋愛番組のオリジナルコンテンツが豊富。 |
VODのおすすめポイント
- U-NEXT: アニメ以外にもラノベやマンガが楽しめる。ポイント還元で実質的なコストを抑えられる。
- Amazonプライム: コストパフォーマンスが高く、独占配信が魅力。Amazon利用者には特に便利。
- ABEMAプレミアム: 地上波作品の視聴やオリジナルコンテンツが充実。テレビ番組やニュースも楽しめる。
特にABEMAをおススメ!月額料金は960円。
無料放送も多く、コンテンツも充実しています。VODだけじゃなくテレビ番組やニュースも豊富なんでおススメです。
☟アニメ見るならここがおすすめ

☆☆☆☆☆今回はここまで。
👇これ!面白い
ウマ娘シンデレラグレイ ~序章カサマツ篇・オグリキャップが”怪物”になるまで
👇【2025春アニメ】5/21最新ランキング!覇権候補と注目作を徹底解説!
【アニメ関連はこっちから】
びわおちゃんブログをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。