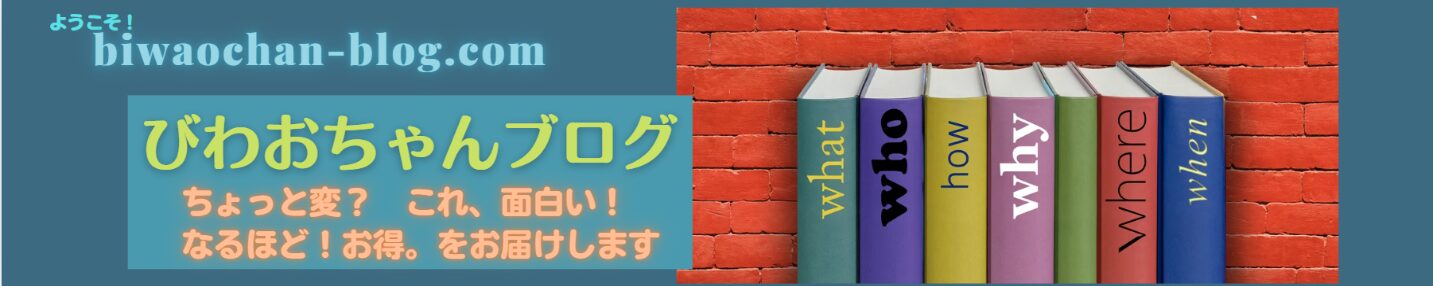こんにちは!びわおちゃんブログ&アニオタWorld!へようこそ。今回は、江戸から平成へ、170年もの長きにわたる鬼人の旅路を描く壮大な和風ファンタジー『鬼人幻燈抄』、第18話「茶飲み話」の感想と考察をお届けします。物語はついに、原作コミックスではまだ描かれていない未知の領域へと足を踏み入れました。慶応三年の京と江戸を舞台に、付喪神使い・秋津染五郎が再登場し、甚夜との間に流れる穏やかな時間の裏で、時代の大きなうねりと新たな鬼の影が静かに忍び寄ります。
特に心に残ったのは、秋津染五郎の退魔の方法です。「派手に切るだけが退魔やないよ。寄り添うのも妖を払う術や」と、物に宿った悲しい想いに寄り添い、その役目を果たさせることで供養する。彼のこの優しさは、ひたすらに刀を振るい、鬼を斬り捨てることでしか前に進めなかった甚夜の孤独な旅路と、鮮やかな対比をなしていました。同じ「人ならざる者」と関わる者でありながら、この二人の在り方の違いは、今後どのような交わりを見せるのでしょうか。彼の存在は、甚夜の心の救いとなり得るのかもしれません。
(ネタバレ注意)本ブログは「鬼人幻燈抄」の理解を促進するための感想・解説・考察に留まらず、ネタバレになる部分を多く含みます。
はじめに:原作未踏の領域へ、静かなる嵐の前の物語
アニメ『鬼人幻燈抄』の物語は、今回の第18話「茶飲み話」から、里見有先生が作画を手がける原作コミックスにもまだ描かれていない、全く新しいエピソードへと突入しました。ファンにとっては、毎週の放送が初見となる、胸躍る展開の始まりです。
ちなみに、心待ちにしている方も多いかと思いますが、原作コミックスに関する嬉しいお知らせがあります。
【解説1:原作コミックス出版予定日】
里見有先生による『鬼人幻燈抄』のコミックス第9巻は、2025年9月10日に発売が予定されています。これは双葉社の公式サイトや公式X(旧Twitter)でも告知されており、多くのファンが発売を待ち望んでいます。さらに、同日には中西モトオ先生の原作小説、文庫版第10巻も発売される予定とのこと。アニメで新たな展開に触れた後、原作の世界でその答え合わせやさらなる深掘りができるのは、私たちファンにとってこの上ない喜びですね。
さて、第18話は、そのタイトル通り、一見すると非常に穏やかなエピソードです。しかし、その静かな水面のすぐ下では、幕末という激動の時代がもたらす渦と、京に潜む新たな妖の気配が、確かに渦巻いています。今回は、この静けさの中に巧みに隠された物語の核心と、登場人物たちの心の揺らぎを、じっくりと考察していきたいと思います。
第18話「茶飲み話」あらすじと登場人物たちの「今」
物語の舞台は、大政奉還が行われる慶応三年(1867年)の九月。物の想いを鬼に変える力を持つ“付喪神使い”の秋津染五郎が、美しい茶器を携えて京から江戸の甚夜を訪ねてきます。

大政奉還は、慶応3年10月14日の出来事です。
西暦に直すと、1867年11月9日にあたります。
この日、江戸幕府の第15代将軍である徳川慶喜(とくがわ よしのぶ)が、政権を朝廷(明治天皇)に返上することを申し出ました。これにより、約260年続いた江戸幕府は終わりを告げ、日本は明治維新へと向かうことになります。
風雲急を告げるこの時代のこの時期が今回の第18話「茶飲み話」の舞台となっているのです。
成長した野茉莉と、再会した秋津染五郎
甚夜の長屋を訪れた秋津を出迎えたのは、小さな女の子。天邪鬼の夕凪から甚夜に託された赤子、野茉莉です。彼女が甚夜のもとに来たのは文久三年(1863年)のことでしたから、今は4歳くらいでしょうか。すっかり大きくなり、甚夜の側で静かに過ごす姿に、時の流れを感じずにはいられません。

秋津は、金粉で紫陽花が描かれた美しい平棗(ひらなつめ)の茶器を甚夜に見せます。しかし、この茶器には曰くがある様子。「人気がのうてなあ」「使われんまま、埃をかぶっとった」と語る秋津。甚夜はその理由を言い当てます。
「紫陽花ではなあ。紫陽花は植えられた土によって花の色を変える。それゆえ、移り気や裏切りを意味する。不義の花とされているのだろう」

それでも秋津は、この茶器で茶を点ててくれる人を探していると言い、甚夜を誘います。「茶を飲みながら雑談しようか、鬼の件や幽霊も含めて」と。二人は野茉莉を馴染みの蕎麦屋「喜兵衛」に預け、茶の心得がある旗本・三浦直次の屋敷へと向かうのでした。
移りゆく時代と変わらぬ存在 – 甚夜と秋津が映す時の流れ
三浦邸へ向かう道中、秋津はふと、寂しさを滲ませた言葉を漏らします。

「まあ、色々あるわなあ。人も、街も。気づいたらどんどん変わっていくし、気づかんでもいつの間にか変わっとる。それが少し寂しい気がすんのは年を取ったせいなんかなあ」
このセリフは、今回のエピソードを象徴する、非常に重要なものです。
秋津の寂寥と甚夜の不変
秋津が前回、第13話「残雪酔夢」(後編)で登場してから、およそ4年の歳月が流れています。人間にとっては決して短くない時間です。蕎麦屋の喜兵衛の店主は少し老け、これから訪ねる三浦直次もまた、旗本としての責務の中で年を重ねていることでしょう。人の世は絶えず移ろい、変わっていく。それが道理です。

しかし、その中で、鬼である甚夜と、同じく鬼である蕎麦屋の看板娘・おふうだけは、時の流れから取り残されたかのように、その姿を変えません。秋津の言葉は、図らずも、彼ら「人ならざる者」の存在を際立たせるのです。友が年を重ねていく様を隣で見つめるしかない甚夜の胸中には、秋津が感じている「寂しさ」とはまた違う、もっと深く、永遠に近い孤独が広がっているのかもしれません。この対比は、本作が描き続ける「鬼として生きる」ことの切なさを、改めて私たちに突きつけます。
骨董屋での一幕 – 物に込められた想いと歴史
秋津は「ついでに花見せえへん?」と甚夜を誘い、道すがらの骨董屋へと足を運びます。ここで繰り広げられる二人の会話は、まさに大人の知的なやり取りであり、歴史や美術を愛する視聴者の心をくすぐるものでした。

器が語る物語と秋津の狙い
秋津は、店内に並ぶ品々を手に取り、その魅力を生き生きと語ります。
- 備前のぐい呑み: 「こいつで酒を飲むと香りが立って味もまろやかになる」
- 九谷の絵皿: 花鳥や山水の美しい絵付けを指し、「器としての魅力とともに絵画としての美しさも持っている」
そして、彼はこうも言います。
「きんこうが成り立ちに関わっとるから秋津としても縁がある」と。
【「きんこう」とは何か?】
ここで秋津が言った「きんこう」は、おそらく「金工」のことでしょう。金工とは、金属を加工して器物や装飾品を作る工芸技術、またはその職人を指します。特に、刀の鍔(つば)や小柄(こづか)といった刀装具を手がける職人は、武士の魂である刀に、美と祈りを込めてきました。
付喪神使いである秋津は、物に込められた作り手の「想い」を誰よりも敏感に感じ取ることができます。金工師もまた、自らの魂を削るようにして作品に想いを込める存在。だからこそ、秋津は金工の仕事に深い縁、シンパシーを感じているのです。背景を知ることで物の見え方が変わる、という甚夜の返しは、まさにその通りですね。

そして、秋津は一枚の皿の前で感嘆の声をあげます。「こいつが僕のお目当てや。鍋島、色絵芝垣桜紋皿。見事なもんやろう」と。彼は、すべての物に作り手の想いや祈りが込められていると語り、こう締めくくります。
「季節外れでもこれなら関係あらへん。100年前も変わらず、100年後も残る花や」
この言葉は、移ろいゆく人の世と対比される、芸術品という「変わらないもの」への賛美です。そしてそれは、170年という時を生き続ける甚夜自身の存在にも、静かに重なっていくのです。
茶席に揺れる静かな波紋 – 過去の記憶と現在の思惑
舞台は三浦直次の屋敷へ。直次が点てる茶を前に、三人の間には穏やかな、しかしどこか緊張感をはらんだ空気が流れます。そして、甚夜の脳裏には、遠い過去の記憶が蘇るのでした。

甚夜の回想 – 幼き日の葛野と謎の少女たち
甚夜が思い出すのは、幼い頃、故郷の葛野で白雪たちと川に飛び込んで遊んだ、眩しい夏の日の光景です。真っ先に飛び込む活発な白雪、それに続く甚太。そして、鈴音ともう一人の見知らぬ少女。この、名前も明かされなかった少女は一体誰だったのでしょうか。

さらに、もう一つの記憶が蘇ります。庭で蟻の行列を眺める幼い鈴音。生垣の向こうから「ちとせちゃん、見て見て」と楽しげな声が聞こえ、鈴音がそっと覗くと、同年代の二人の少女が野の花を愛でています。そのうちの一人、「ちとせ」と呼ばれた少女に気づかれた鈴音は、怯えたように家の中に逃げ込んでしまいます。


【「ちとせ」とは誰か?】
この回想シーンに登場した「ちとせ」という少女は、現時点では何者なのか一切不明です。しかし、このシーンが持つ意味は明らかでしょう。それは、鈴音の深い孤独です。彼女は、他の子供たちの輪に入ることができず、ただ遠くからその楽しげな様子を眺めることしかできませんでした。鬼の子であるという出自が、彼女を幼い頃から苛み、孤立させていたのです。この孤独と疎外感が、後に彼女を鬼へと駆り立てる一因となったことは想像に難くありません。「ちとせ」は、鈴音が手に入れることのできなかった「普通の子供の日常」の象徴として、強く印象に残ります。
「知己というほど親しくない」- 甚夜の真意とは
穏やかな茶席の最中、一つの謎めいたやり取りが交わされます。直次が秋津のことを「壬殿の知己」と評したことをきっかけに、甚夜はふと、こう呟くのです。
「知己というほど染五郎とは親しくないな」

【なぜこのタイミングで甚夜は語ったのか】
この発言は、一見すると唐突で、会話の流れを断ち切るかのようです。直次が話題にしていたのは、秋津と壬生浪士組(新選組)との繋がりであり、甚夜と秋津の関係ではありませんでした。では、なぜ甚夜はあえてこのタイミングで、秋津との関係性について口にしたのでしょうか。
これは、直後の直次のセリフ「できればこのまま変わらず続けていきたい」という、甚夜との「縁」を大切にしたいと語った言葉に繋がっていきます。直次が「縁」や「関係性」について思いを馳せているのを見て、甚夜の意識もまた、隣にいる秋津との関係へと向かったのではないでしょうか。
甚夜と秋津は、互いに深いところで理解し合いながらも、決して馴れ合うことのない、独特の距離感を保った関係です。それを、安易に「知己(親友)」という一言で括られることへの、甚夜なりの小さな抵抗だったのかもしれません。あるいは、人との「縁」をどこか諦観している鬼である彼が、それでも秋津との繋がりを意識していることの、不器用な表れだったとも考えられます。この一言に、彼の複雑な内面が凝縮されているようで、非常に心を揺さぶられます。
幕末の不穏な影 – 直次の決意と甚夜の洞察
茶席の後、直次は甚夜に京の様子を尋ねます。秋津は「長州やら薩摩やら元気なお客さんが来てわやくちゃですわ」と冗談めかして答えますが、その言葉に直次の顔は曇ります。
三浦邸を辞す甚夜を、直次は呼び止めます。「近々稽古をつけてもらいたいのですが」と。

【直次の決意と甚夜の洞察】
この場面の直次は、明らかに何か大きな決意を固めています。彼が何を思って甚夜に稽古を依頼したのか。それは、秋津がもたらした京の不穏な情報と無関係ではないでしょう。慶応三年は、まさに幕府の権威が失墜し、倒幕の動きが激化する直前の時期。旗本である直次は、時代の大きな変化を肌で感じ、来るべき動乱の中で、幕臣として、あるいは一人の武士として、自らの役割を全うする覚悟を決めたのではないでしょうか。そのために、達人である甚夜の剣を学び、己を鍛え上げておきたい。それが彼の願いだったのです。「いずれ、時が来れば」という彼の言葉は、その「動乱の時」が来たならば、自分の覚悟を打ち明けるという意味に他なりません。
一方の甚夜も、そのすべてを察しています。「稽古は構わないが力になれることがあれば言え」という言葉は、単なる優しさではありません。彼は、直次の瞳の奥に宿る悲壮な覚悟と、そこに付きまとう死の匂いを、人ならざる者の鋭い感覚で見抜いていたのです。友が死地へ向かおうとしているのを、ただ見守ることしかできない。ここにもまた、甚夜の深い苦悩が垣間見えます。
京に渦巻く妖気と静かに迫る「鬼女」の影
夕暮れの道を、甚夜と秋津は肩を並べて歩きます。ここでようやく、秋津が江戸に来た本当の目的が語られます。

秋津がもたらした不吉な噂
「雑談は終わり。次は鬼の話やね」
秋津によると、近頃の京は物騒で、それに呼応するように妖の類が溢れかえっているというのです。さらに、退魔師の間では「妖の頭目みたいなもんがおるんやないか」という不吉な噂が流れていると。
甚夜が「そいつの特徴、例えば髪の色は?」と問うと、秋津は「さあ?」と首を傾げ、こう続けました。
「そいつが屈強な怪異か、あるいは鬼女か…」
「鬼女」という言葉に、甚夜は鋭く反応します。彼の脳裏をよぎったのは、言うまでもなく、かつて愛する白雪をその手で殺めた、鬼と化した妹・鈴音の姿でした。京で噂される妖の頭目と、鈴音は何か関係があるのでしょうか。物語は、新たなミステリーの幕を開けたのです。

茶器に宿る優しい幽霊 – 付喪神使いの粋な供養
鬼の不穏な話の後、秋津はもう一つの「本題」も片付いたと言います。それは、彼が持ってきた平棗の茶器にまつわる「幽霊」の件でした。


【秋津染五郎に払われた幽霊の正体】
秋津が語るには、この茶器は紫陽花の意匠が不吉だとされ、持ち主を転々とし、ついには一度も使われないまま持ち主も亡くなり、空き家に捨てられていたといいます。そして「かわいそうになあ。せっかく可愛く作ってもらったのに」と。使われることなく忘れ去られた茶器自身の「想い」が形を持ち、幽霊となっていたのです。
秋津がしたことは、その幽霊を斬り捨てることではありませんでした。彼は、この茶器を使って茶を点ててくれるにふさわしい人物(三浦直次)を探し出し、茶席を設け、茶器本来の役目を果たさせてやったのです。さらに、骨董屋で様々な美しい器を見せたのも、この茶器に宿る霊に「仲間」を見せて喜ばせてやるためでした。
「派手に切るだけが退魔やないよ。寄り添うのも妖を払う術や」
この秋津の言葉こそ、彼の真骨頂です。物の想いを鬼に変える付喪神使いだからこそできる、最高に粋で、優しい供養の形でした。彼の掌で愛おしそうに撫でられた茶器から、光の粒が舞い上がり天に消えていくシーンは、今回のエピソードで最も美しく、心温まる瞬間だったと言えるでしょう。

作画への期待と一抹の不安
物語のラスト、甚夜は野茉莉を迎えに蕎麦屋「喜兵衛」を訪れます。蕎麦を食べた感想を聞かれ「えっと、普通」と答える野茉莉のシュールな姿に、思わず笑みがこぼれます。
ここで、甚夜が野茉莉の口元についたそばつゆを手ぬぐいで拭うシーンがありました。一瞬、汚れが拭き取れておらず、次のカットで消えているという、ほんの些細な作画の乱れが見られました。
(さらに言えば今回の18話は不自然なまでに静止画が多かった気がしています)


【制作会社への小さな懸念】
このアニメの制作を手がけるのは、横浜アニメーションラボです。過去のブログでも触れたように、同社が関わった「ささやくように恋を唄う」で制作上のトラブルがあったことから、一部のファンの間では常に一抹の不安が囁かれています。
もちろん、『鬼人幻燈抄』は全体を通して非常に高いクオリティを維持しており、特に背景美術やキャラクターの表情の機微などは見事というほかありません。今回の些細なミスも、物語の評価を損なうものでは決してありませんが、それゆえに「どうかこのクオリティを最後まで保ってほしい」と願わずにはいられないのです。これは、本作を愛するファンだからこその、切なる祈りのようなものかもしれませんね。
まとめ – 静かな日常に潜む嵐の予兆
第18話「茶飲み話」は、秋津との再会や野茉莉の成長といった心温まる日常風景を描きながら、その裏で進行する幕末の動乱、京に潜む鬼の頭目の影、そして直次の悲壮な決意といった、今後の嵐を予感させる要素を巧みに織り込んだ、実に見事な構成のエピソードでした。
物に込められた想いを巡る物語は、人の想いが交錯する歴史の物語へと繋がり、静かな茶室での一コマは、やがて血風吹き荒れる激動の時代への序曲であったことを、私たちに静かに教えてくれているようでした。
特に心に残ったのは、秋津染五郎の退魔の方法です。「派手に切るだけが退魔やない」と、物に宿った悲しい想いに寄り添い、その役目を果たさせることで供養する。彼のこの優しさは、ひたすらに刀を振るい、鬼を斬り捨てることでしか前に進めなかった甚夜の孤独な旅路と、鮮やかな対比をなしていました。同じ「人ならざる者」と関わる者でありながら、この二人の在り方の違いは、今後どのような交わりを見せるのでしょうか。彼の存在は、甚夜の心の救いとなり得るのかもしれません。

そして、物語は私たちに新たな謎を投げかけます。京に潜むという「鬼女」の正体。それは、170年の時を経て現れると予言された、甚夜の妹・鈴音なのでしょうか。旗本としての覚悟を決めた三浦直次の未来は、歴史の荒波の中でどうなってしまうのか。さらに、甚夜の脳裏をよぎった、幼き日の記憶と「ちとせ」という少女の謎。これら無数の伏線が、今後の物語をより深く、より複雑に彩っていくことでしょう。
一見、穏やかな「茶飲み話」は、実は物語の次なるステージへ向かうための、非常に重要な布石が打たれた回でした。束の間の平穏が終わりを告げ、甚夜は再び、逃れられぬ宿命の渦中へと身を投じていくことになります。彼の長い旅路の先に待つものを、これからも一緒に見届けていきましょう。
『鬼人幻燈抄』の世界を深く味わう!待望の新刊&Blu-ray BOX発売
アニメも絶賛放送中、170年にわたる壮大な旅路を描く和風ファンタジー『鬼人幻燈抄』。ファン待望のコミックス&原作小説の最新刊が2025年9月10日に同時発売!さらに、物語の全てを収録したBlu-ray BOXも登場です。
【コミックス最新刊】鬼人幻燈抄 第9巻
里見有先生の美麗な筆致で描かれるコミカライズ版、待望の第9巻!
舞台は元治元年(1864年)、幕末の動乱期。甚夜のもとに舞い込んだのは、人斬りと化した鬼・岡田貴一を討ってほしいという依頼でした。歴史の大きなうねりの中で、甚夜は新たな鬼との死闘に身を投じます。アニメのあのシーンを漫画で追体験したい方、そしてその先の物語をいち早く見届けたい方におすすめです!
【原作小説最新刊】鬼人幻燈抄 文庫版 第10巻『大正編 夏雲の唄』
中西モトオ先生が紡ぐ物語の原点、文庫版の最新第10巻『大正編 夏雲の唄』が登場します。
南雲叡善の企みを阻止した甚夜でしたが、彼の故郷・葛野の記憶に繋がる「鬼哭の妖刀」が持ち去られてしまいます。失われた大切なものを取り戻すため、物語はついに大正編のクライマックスへ! 小説ならではの緻密な心理描写と重厚な世界観を、ぜひご堪能ください。
【永久保存版】鬼人幻燈抄 Blu-ray BOX
江戸から平成へ、甚夜の170年にわたる孤独な旅を描いたアニメ全24話。その全てを1BOXに完全収録したBlu-ray BOXで、感動の名場面を何度でも。高画質な映像美で蘇る壮大な物語は、まさに永久保存版。お手元でじっくりと『鬼人幻燈抄』の世界に浸ってみませんか。
☆☆☆☆☆今回はここまで。
👉使用した画像および一部の記述はアニメ公式サイトから転用しました。
【アニメ関連はこっちから】
びわおちゃんブログをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。