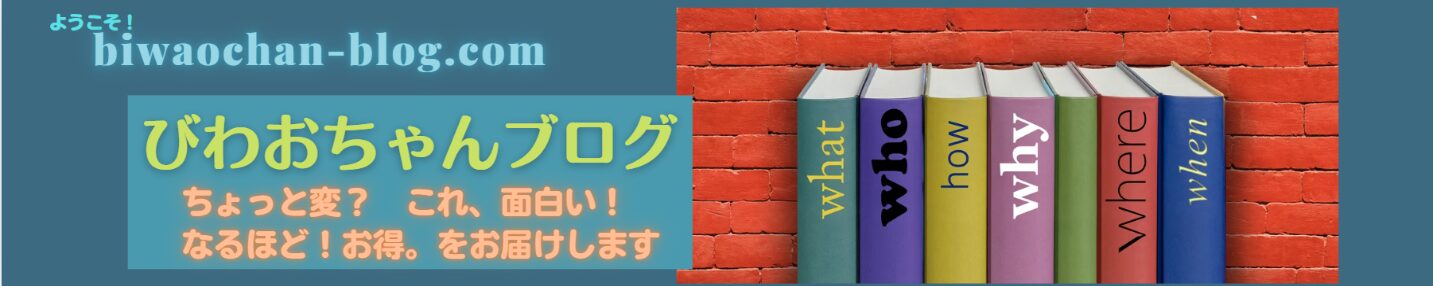こんにちは!びわおちゃんブログ&ヴェゼルでお出かけ!へようこそ。
宮崎での1泊2日の旅も、いよいよ最終日を迎えました。昨夜は都城グリーンホテルで、「みやこんじょミート券」を駆使したお得で美味しい夕食と、評判通りの豪華な朝食バイキングを堪能し、心身ともに満たされた朝です。
👇昨夜の都城ルポはこちら!
往路は東九州自動車道をひたすら南下して都城まで来ましたが、帰路は少し趣向を変えてみることにしました。「まっすぐ帰るだけでは芸がないな」と、奥さんと相談し、一般道で宮崎の内陸部を巡るルートを選択。私たちの新しい愛車ヴェゼルは、緑豊かな綾町、そして古代ロマンあふれる西都市へとハンドルを切りました。
今回は、旅の終わりを飾るにふさわしい、宮崎が誇る絶景と歴史を巡る寄り道の記録です。
天空の散歩道「綾の照葉大吊橋」で深緑の絶景に息をのむ
都城の市街地を抜け、ヴェゼルを走らせること約1時間。車窓を流れる風景は、次第に緑の色を濃くしていきます。目指すは、宮崎県綾町に架かる「綾の照葉大吊橋(あやのてるはおおつりはし)」です。
高さ日本一!かつて世界を誇った天空の架け橋
駐車場に車を停め、森の空気が漂う遊歩道を歩いていくと、木々の合間から巨大な吊り橋の姿が目に飛び込んできました。

- 高さ:水面から142メートル
- 長さ:250メートル
特筆すべきはこの高さです。なんと、歩道吊り橋としては日本一の高さを誇ります。かつて1984年の完成当時は世界一の規模だったと聞きますから、その壮大さは推して知るべしです。その後、国内外にさらに大きな吊り橋が建設され「世界一」の称号は譲りましたが、今なお「高さ日本一」の座を守り続けていることに、かえって誇らしさを感じます。
この橋の真価は、その高さや長さといったスペックだけではありません。眼下に広がる、どこまでも続く深い緑の森。これこそが、綾町が世界に誇る「照葉樹林」です。

【コラム】太古の森の息吹 ― なぜ「綾の照葉樹林」は世界的にも貴重なのか?
私たちが吊り橋の上から眺めたあの森は、ただの「緑の森」ではありません。それは、数千年前の日本の姿を今に伝える、極めて貴重な「照葉樹林」です。
そもそも「照葉樹林」とは?
照葉樹林とは、その名の通り、葉の表面がクチクラ層で覆われ、光を照り輝かすように見える常緑広葉樹で構成された森林のことです。主にシイ、カシ、タブノキといった樹木が主体で、冬でも葉を落とさないため、一年中深い緑を保ちます。
かつて、この照葉樹林は西日本の平地から低山地を広範囲に覆っており、縄文時代の人々もこの森の恵みと共に暮らしていたと考えられています。しかし、開発によってそのほとんどが失われ、原生的な姿を残す森はごくわずかになってしまいました。
「綾の照葉樹林」が特別な理由
その中で、宮崎県綾町に残る照葉樹林は、日本最大級の規模を誇ります。これほどまとまった原生的な照葉樹林は世界的にも類がなく、学術的にも極めて価値が高いとされています。

この価値が世界的に認められたのが、2012年の「ユネスコエコパーク」への登録です。単に自然を「保護」する世界遺産とは異なり、エコパークは「自然と人間社会の共存」を目指す取り組みです。綾町が半世紀以上にわたり、森を守りながら有機農業や手づくり工芸といった産業を育んできた、その営み全体が評価されたのです。
未来へつなぐ「綾の照葉樹林プロジェクト」
さらに、この貴重な森を守り、かつての姿に復元するための壮大な取り組みが「綾の照葉樹林プロジェクト」です。これは、国や県、町、そして専門家や市民団体が協働し、照葉樹林の周囲に広がるスギやヒノキの人工林を、再び照葉樹の森へ復元していくプロジェクトです。
驚くべきはその手法で、単に苗木を植えるのではありません。人工林を間伐して林内に光を入れ、残された照葉樹林から種が自然に飛んでくるのを待ち、森が自ら再生する力を助けるという、気の遠くなるような時間をかけた方法が採られています。近年はシカの食害という課題にも直面しながら、防獣ネットの設置やドングリの植樹などで対策が続けられています。
私たちが吊り橋から見た森は、太古の自然の姿であると同時に、綾の人々が未来へとつなごうとしている、希望の森でもあるのです。
一歩踏み出せば、そこは緑の海の上

大人一人350円の入場券を買い、いよいよ橋の上へ。一歩足を踏み出すと、足元のグレーチング(網目状の床板)から、はるか142メートル下の綾南川の渓谷が透けて見えます。これはなかなかのスリルで、高所が得意ではない人は少し足がすくむかもしれません。奥さんも私も、思わず手すりをしっかりと握りしめてしまいました。

しかし、勇気を出して顔を上げ、周囲を見渡した瞬間に広がる光景は、そんな恐怖心を忘れさせてくれるほどの絶景です。視界を埋め尽くす360度の原生林。まるで広大な緑の海の上を歩いているかのような錯覚に陥ります。風が木々を揺らす音と鳥のさえずりだけが聞こえる静寂の中、自然との一体感を味わうことができました。約2時間の滞在中、私たちは橋を渡り、展望台からの眺めを楽しみ、この雄大な自然の空気を心ゆくまで満喫しました。

日本最大級の照葉樹林とユネスコエコパーク

綾町は、かつて「日本一の照葉樹林の町」として町おこしを行っていました。照葉樹林とは、シイやカシ類など、冬でも葉が落ちず、葉の表面が光沢を放つ常緑広葉樹で構成される森林のことです。かつては西日本の広い範囲を覆っていましたが、開発によりその多くが失われ、ここ綾町には日本最大級の原生的な森が奇跡的に残されています。
そして、この貴重な自然と、それを守りながら共存してきた地域社会の営みが評価され、2012年には「ユネスコエコパーク」に登録されました。「自然遺産」が手付かずの自然の「保護」を目的とするのに対し、「エコパーク」は「自然と人間社会の共存」を目指すものです。長年にわたる地域住民の保護活動が、世界的な評価を得たのです。この吊り橋は、単なる観光施設ではなく、自然の価値と人間との共存のあり方を体感させてくれる場所でもありました。
散策に役立つ施設情報
吊り橋周辺には、散策をより楽しむための施設が整っています。

| 施設名 | 内容 |
|---|---|
| 綾の照葉大吊橋 | 入場料: 大人 350円、高校生 250円、小・中学生 150円 営業時間: 8:30~17:00(季節により変動あり) |
| 照葉樹林文化館 | 吊り橋のそばにある入館無料の資料館。綾の照葉樹林の生態系や、森と人々の関わりの歴史を学べます。吊り橋を渡る前に立ち寄ると、景色の見え方が変わってくるのでおすすめです。 |
| 物産館「綾陽館」 | 吊り橋入口の売店。綾町産の新鮮な農産物や、日向夏ドリンクなどの特産品が並びます。ドライブのお供を探すのに最適です。 |

古代への誘い「西都原古墳群」で歴史と秋の風景に浸る
綾町で心洗われる時間を過ごした後、私たちは再びヴェゼルに乗り込み、古代の王たちが眠る地、西都市へと向かいました。綾町からは車で約40分ほどの距離です。目指すは、国の特別史跡に指定されている「西都原(さいとばる)古墳群」です。

古代日向の中心地 – なぜこの地に巨大古墳群が築かれたのか
西都原古墳群の広大な敷地に足を踏み入れると、誰もが「なぜ、これほど多くの巨大な古墳がこの場所に集中しているのか」という疑問を抱くことでしょう。その答えは、この土地が持つ地理的・政治的な重要性にあります。
西都原は、宮崎平野のほぼ中央に位置する標高50~80メートルの洪積台地です。この台地は、古代において人々が暮らす上で、いくつかの決定的な優位性を持っていました。
- 豊かな穀倉地帯: 台地のすぐそばを流れる一ツ瀬川は、しばしば氾濫を繰り返す「暴れ川」でしたが、同時に肥沃な沖積平野を形成しました。これにより、安定した稲作が可能となり、多くの人口を養う経済的基盤が生まれました。
- 防御に有利な地形: 台地上は平坦で広大ですが、周囲は川や崖によって切り立っており、まさに**「天然の要塞」**でした。外敵からの防御が容易であると同時に、水害の心配もありませんでした。
- 交通の結節点: 宮崎平野を南北に貫く古代の幹線道路がこの地を通り、さらに一ツ瀬川を利用した水上交通の拠点でもありました。つまり、西都原は陸路・水路の双方が交わる交通の要衝であり、人・モノ・情報が集まる場所だったのです。
豊かな経済力と、外敵から人々を守る堅牢な地形、そして広域を支配する上で欠かせない交通の便。これらの条件が揃った西都原は、古代日向の国の中心地として栄え、強大な権力を持つ豪族(王)が登場する舞台となりました。そして、その王たちが自らの権威を内外に示すために築いたのが、この巨大な古墳群だったのです。西都原古墳群は、単なる墓域ではなく、古代日向の一大政治センターであったことの証と言えるでしょう。
また、西都原が位置する西都市一帯には、西都原古墳群のほか、記紀神話に登場するニニギノミコトとコノハナサクヤヒメの陵墓と伝わる男狭穂塚(おさほづか)・女狭穂塚(めさほづか)古墳群など、複数の古墳群が点在しており、これらを総称して**「西都(さいと)古墳群」**と呼びます。この広域にわたる古墳の分布からも、この地域が長期間にわたり、南九州における政治・文化の中心であったことがうかがえます。
400年の歴史を物語る「西都原古墳群」の概要
特別史跡「西都原古墳群」には、3世紀後半から7世紀にかけての約400年間にわたり築造された、311基もの古墳が保存されています。前方後円墳、円墳、方墳など、様々な形と大きさの古墳が広大な台地の上に点在する光景は圧巻です。

敷地内には、古墳について学べる施設も充実しています。
- 西都原考古博物館: なんと入場無料で、古墳からの出土品や精巧なジオラマを見ることができます。私たちは過去に何度か訪れたことがあるため、今回は立ち寄りませんでしたが、初めて訪れる方にはぜひおすすめしたい施設です。古代人の暮らしや技術の高さをリアルに感じることができます。
- このはな館: 観光案内や休憩、食事ができるガイダンスセンターです。古代食をイメージしたメニューなども楽しめます。
秋風に揺れるコスモスと、石室を覗ける「鬼の窟古墳」
私たちが訪れた11月上旬、台地の一角は300万本のコスモスで埋め尽くされていました。ピンクや白の花々が秋の小春日和の光を浴び、風にそよぐ様は、まるでピンク色の絨毯のよう。古墳群の持つ悠久の歴史と、可憐な花々のコントラストが、何とも言えない美しい風景を創り出していました。
私たちは、そのコスモス畑の中をゆっくりと散策。すると、畑の中にこんもりとした円墳があるのに気づきました。それが、「鬼の窟(おにのいわや)古墳」です。この古墳は横穴式石室を持っており、石室の内部が公開されています。屈んで中に入ると、千数百年前に築かれた石積みの部屋を間近に見ることができ、ひんやりとした空気が古代の息吹を伝えてくるようでした。

古墳時代後期の6世紀後半から7世紀初頭にかけて造られたこの古墳は、西都原での古墳時代の終焉を象徴する存在でもあります。

西都原古墳群の歴史年表
400年にわたる古墳群の歴史を、簡単な年表にまとめました。
| 時代 | 時期 | 主な出来事・特徴 |
|---|---|---|
| 古墳時代 前期 | 3世紀後半~4世紀 | 古墳の築造が始まる。前方後円墳が出現する。 |
| 古墳時代 中期 | 5世紀 | 古墳の築造が最も盛んになる。九州最大級の前方後円墳「男狭穂塚」が築かれる。権力の最盛期。 |
| 古墳時代 後期 | 6世紀~7世紀 | 古墳の巨大化が終わり、小規模な円墳が多数造られる(群集墳)。大陸から伝わった横穴式石室を持つ古墳(鬼の窟古墳など)が登場する。古墳の築造が終焉を迎える。 |
| 近代・現代 | 1912年~1917年 | 日本で初めて本格的な考古学的調査が行われる。 |
| 現代 | 1952年 | 国の特別史跡に指定される。 |
| 現代 | 1995年 | 西都原考古博物館が開館する。 |
名残を惜しみつつ帰路へ
綾の大吊り橋と西都原古墳群で、それぞれゆったりと時間を過ごし、時計の針はすでに午後4時を指していました。今回は、観光地を駆け足で巡るのではなく、一つ一つの場所で心ゆくまで秋の日差しと歴史のロマンを楽しむ、のんびりとした行程となりました。
後ろ髪を引かれる思いで西都市を後にし、私たちは再び都農ICから東九州自動車道に乗り、大分への帰路についたのでした。新しい愛車ヴェゼルと共に巡った宮崎の旅は、絶景、歴史、そして美味しいグルメに満ちた、忘れられない思い出となりました。
☆☆☆☆☆今回はここまで。またね👋
びわおちゃんブログをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。