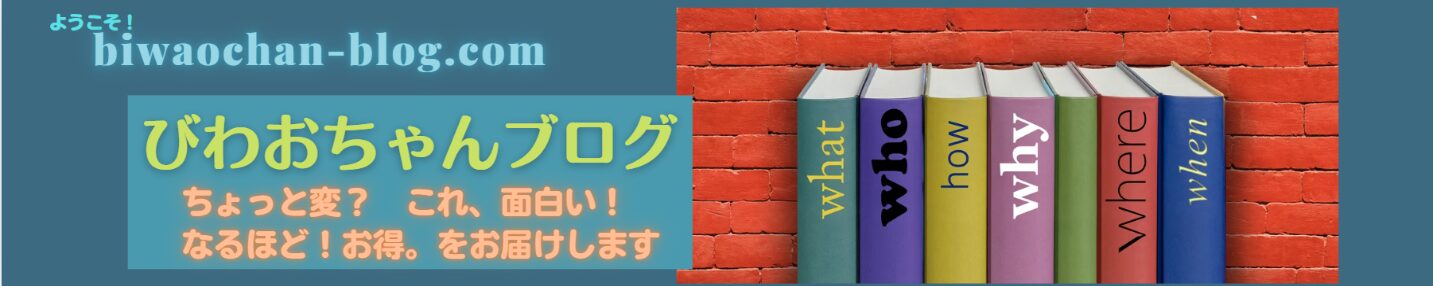日産がホンダからの子会社化の提案を拒否
2025年2月5日、日産自動車は午後に取締役会を開き、ホンダからの子会社化提案を拒否する方向で進めるとの報道がありました。この動きは、両社の経営統合に向けた協議に大きな影響を及ぼす可能性があります。ホンダは日産に対して、株式を取得して子会社化する案を提示していましたが、日産内部では反対意見が多く、取締役会での拒否が濃厚とされています。
この状況は、日産にとって非常に厳しいものです。日産は現在、北米や中国市場での販売不振に直面しており、最近の中間決算では営業利益が90%以上減少するという深刻な経営危機にあります。さらに、三菱自動車の業績悪化も明らかになり、日産の経営に対する信頼性が低下しています。三菱自動車は2025年3月期の純利益見通しを77%減に下方修正し、業績の悪化が続いています。このような状況下で、日産がホンダとの統合を進めることは、さらなるリスクを伴う選択となります。
ホンダと日産は、昨年12月に共同持ち株会社の設立を発表し、2026年8月の上場を目指して協議を進めていました。しかし、日産が大株主である三菱自動車が合流を見送る方向で調整に入ったことが報じられ、統合の計画自体が危ぶまれる事態となっています。ホンダの子会社化提案が拒否されることで、両社の関係が悪化し、統合計画が破談になる可能性も出てきました。
日産の内田社長は、両社の関係を「ともに未来を切りひらく仲間」と表現していましたが、ホンダの提案が対等の精神を超えたものであったため、日産の取締役会が拒否することで、これまでの枠組みが崩れることになります。日産にはホンダの案に賛成する幹部もいるとのことですが、取締役会での結論がどのようになるかは流動的です。
このような状況を受けて、日産の米国預託証券(ADR)は急落し、ホンダ株も一時下落に転じる場面がありました。
☞ニュースソースと写真はブルームバーグより

日産、ホンダとの経営統合に向けた基本合意書を撤回
2月5日、日産自動車はホンダとの経営統合に向けた基本合意書(MOU)を撤回する方針を固めました。日経新聞が14:42にスクープしています。
記事を要約します。
日産自動車は、ホンダとの経営統合に向けた基本合意書(MOU)を撤回する方針を固めました。両社は持ち株会社方式での統合を検討していましたが、統合比率などの条件が折り合わず、協議が難航していました。ホンダは日産の子会社化案を打診しましたが、日産社内で強い反発が起きたため、協議の打ち切りを決定しました。
当初、両社は2024年12月に経営統合に向けた協議を開始し、2025年6月の最終合意目指していました。しかし、日産の業績不振が影響し、再生プランの策定が遅れていたことが背景にあります。ホンダは日産の立て直しに時間がかかると判断し、子会社化を提案しましたが、日産は対等な経営統合を望んでおり、意見の隔たりが大きくなりました。
今後、両社は統合協議を再開するか、電気自動車(EV)などの協業を継続するかを検討する予定です。
日産は一体何をしたいんでしょうか?
本日の報道を受けたホンダと日産自動車の株価についてお知らせします。
ホンダの終値は1,500円。前日対比8.19%プラスの急騰。
日産自動車の終値は386.9円。前日対比4.87%低下の低迷。
そもそも日産自動車の株価はホンダの4分の1。
今回の経営統合のニュースが流れる前の水準では5分の1です。
日産、何をかいわんや、ですね。
三菱自動車が大幅な業績下方修正を発表
奇しくも前日の2月4日、日産自動車の子会社、三菱自動車の大幅な業績悪化が判明しました。
3月期の純利益見通しを77%減に下方修正
三菱自動車は2025年3月期の連結純利益見通しを77%減の350億円に下方修正したと発表しました。これは、従来の予想である1440億円から1090億円の大幅な修正です。主な要因として、東南アジア市場での販売不振や、米国での競争激化による販売奨励金の増加が挙げられます。また、円安によるコスト増やタイでの人員削減も影響しています。売上高は1%減の2兆7600億円、営業利益は35%減の1250億円と見込まれています.
加藤隆雄社長は、販売費の増加が想定以上であり、為替の影響も大きく悪化したと述べ、タイでは300人の早期退職を募集することを明らかにしました。新車需要の正常化には時間がかかる見込みで、構造改革を前倒しで進める意向を示しています。
ネガティブインパクトで株価は15%急落
三菱自動車(7211)は、2025年3月期の業績見通しを大幅に下方修正し、市場の予想を大きく下回る結果となりました。特に、10〜12月期の営業利益は139億円で、前年同期比で75.2%減少し、550億円程度の市場予想を大きく下回りました。通期の営業利益予想も従来の1900億円から1250億円に引き下げられ、前期比で34.5%の減少が見込まれています。市場コンセンサスは1850億円程度であったため、今回の修正は市場にとって想定外の悪化を示しています.
この業績悪化の要因としては、タイでの部品価格の高騰や為替の影響、さらにはサプライヤーへの支援が挙げられています。これにより、株価は前日比で▲15%の急落を記録しました。市場では、想定以上の業績悪化がネガティブなインパクトを与えているとの見方が強まっています。

ホンダとの経営統合を目指す日産自動車へ悪影響
三菱自動車の業績悪化は、ホンダと経営統合を目指す日産自動車に対して悪影響を及ぼす可能性があります。以下のポイントを考慮する必要があります。
1. 三菱自動車の業績悪化
三菱自動車は最近、2025年3月期の業績見通しを大幅に下方修正しました。特に、10〜12月期の営業利益は前年同期比で75.2%減少し、通期の営業利益予想も従来の1900億円から1250億円に引き下げられました。この業績悪化は、タイでの部品価格の高騰や為替の影響、さらにはサプライヤーへの支援が影響しているとされています.
2. 日産自動車への影響
日産自動車は、三菱自動車の筆頭株主であり、三菱の業績悪化は日産の経営にも影響を与える可能性があります。日産は現在、経営統合に向けた協議を進めており、三菱自動車の業績が悪化することで、統合のメリットやシナジー効果が疑問視されることが考えられます。特に、日産が三菱自動車の経営に対してどのように関与するかが焦点となります.
3. 経営統合の進展
ホンダと日産の経営統合に関する協議は進行中ですが、三菱自動車の業績悪化が統合の進展に影響を与える可能性があります。三菱自動車の加藤社長は、ホンダと日産の協議の進展を見極めた上で、経営統合への参加を判断する意向を示していますが、業績の悪化が統合の決定にネガティブな影響を及ぼすかもしれません。
三菱自動車の業績悪化は、ホンダと日産の経営統合に対して悪影響を及ぼす可能性が高いです。特に、三菱自動車の経営状況が日産の統合戦略にどのように影響するかが注目されます。日産は、三菱自動車の業績を考慮しながら、統合の方向性を慎重に検討する必要があります。
ホンダは日産自動車を見捨てろ
憂慮される日産自動車の経営状況
ホンダが日産との経営統合を取りやめるべきかどうかを考える際、日産の経営状況を慎重に考慮する必要があります。日産自動車は現在、北米や中国市場での販売不振に直面しており、最近発表された中間決算では営業利益が前年同期比で90%以上減少するという深刻な経営危機に陥っています。このような状況下で、日産は全世界での生産能力を20%削減し、9000人の人員削減を計画していますが、具体的な再建策はまだ明らかになっていません。
日産の経営不振は、ホンダとの統合に対するリスクを増大させる要因となります。日産の業績が回復しない限り、ホンダが統合を進めることは、ホンダ自身の経営にも悪影響を及ぼす可能性があります。特に、日産のリストラ策が不十分であるとの指摘もあり、ホンダが期待するシナジー効果が得られないリスクが高まっています。
さらに、日産の経営危機は、ホンダが目指すEV市場での競争力強化にも影響を与える可能性があります。ホンダは2040年までに新車販売のすべてをEVとFCVにする方針を掲げていますが、日産との統合が実現した場合、日産の経営不振がホンダのEV戦略にどのように影響するかは不透明です。
このような状況を踏まえると、ホンダは日産との経営統合を進めるべきかどうかを慎重に検討する必要があります。日産の経営再建が進展し、安定した業績が見込まれるようになるまで、統合を見送る選択肢も考慮すべきでしょう。
合併を必須の選択肢としたホンダの危機感
両社の経営統合の協議が打ち切られる可能性が浮上している中、日産は今後どのように経営を立て直していくのか。
ホンダにとっても、日産自動車との経営統合は単なる救済策ではなく、戦略的な意味合いを持つ重要なステップです。ホンダは、現在の自動車業界における競争の激化と、内燃機関からEV(電気自動車)への移行という大きな変革に直面しています。このような状況下で、ホンダは規模の拡大と新たな効率経営の確立を狙っています。
具体的には、ホンダは伝統的な内燃機関とEV、さらにはソフトウェアへの二重投資がもたらす経営効率の悪化を懸念しています。日産との経営統合によって、規模を確立し、広範なシナジーを生み出すことで、これらの課題を克服しようとしているのです。両社の利害は一致しており、日産もまた経営の安定化と構造改革に集中する必要があるため、ホンダとの統合は双方にとって有益な選択肢となります。
ホンダは、2025年1月に開催されたテクノロジー見本市「CES」で、次世代EV「ゼロシリーズ」や自動運転技術に関する意欲的な発表を行いました。これらの技術は、テスラや中国の自動車メーカーが主導する「自動運転×EV」の革新に匹敵するものであり、ホンダは自らの存在価値を高めるために、テスラに近い方向へとシフトしようとしています。この戦略を実現するためには、日産との経営統合が不可欠であり、規模の拡大がその基盤となるのです。
このように、ホンダにとって日産との経営統合は、単なる救済策ではなく、未来の競争力を確保するための重要な戦略であることが明らかです。両社が協力し合い、規模と効率経営を確立することで、変革の波に乗り遅れないようにすることが求められています。日産との統合が成功すれば、ホンダは自動車業界における競争力を大幅に向上させることができるはずでした。
ホンダは日産を見捨てろ
ホンダにとって、日産自動車との経営統合は、EV市場や自動運転技術の競争で生き残るための必須の選択肢として位置づけられてきました。しかし、日産側の本気度が一向に感じられない現状、さらにその子会社である三菱自動車の業績悪化が明らかになり、統合後の負担が増大するリスクが浮き彫りになっています。このような状況下で、ホンダが取るべき選択肢は、日産との統合に固執するのではなく、柔軟かつ現実的な戦略を再構築することにあるでしょう。
まず、ホンダは日産との統合がもたらすシナジー効果を冷静に再評価し、統合が本当に自社の競争力強化に寄与するのかを見極める必要があります。もし日産側の経営再建が進まず、統合がホンダにとって過度な負担となるのであれば、統合計画の見直しや撤退も選択肢として検討すべきです。
次に、ホンダは単独での成長戦略を強化するため、他のパートナーシップやアライアンスの可能性を模索するべきです。特に、テスラや中国のEVメーカーのような先進的な企業との技術提携や、ソフトウェア分野での外部パートナーとの協力を通じて、EVや自動運転技術の開発を加速させることが重要です。
さらに、ホンダ自身の強みであるハイブリッド技術や次世代プラットフォームの開発を軸に、収益性の高い事業モデルを構築することも急務です。日産との統合が実現しなくとも、ホンダが独自に競争力を高める道筋を描くことは十分可能です。
最終的に、ホンダが取るべき選択肢は、日産との統合に依存するのではなく、自社の未来を切り開くための多角的な戦略を追求することにあります。日産の不透明な姿勢や三菱自動車の足かせが明らかになった今こそ、ホンダは冷静に状況を見極め、柔軟かつ大胆な決断を下すべき時です。
僕の意見です。
もともと持ち株会社設立なんてできないと考えています。
☆☆☆
これにて終了。
次回またお会いしましょう。
👋👋👋
これも見てね!!☟
【旅関連はこっちから】
ヴェゼル関係、アニメ関係、旅関係、なんでもありです。
ブックマーク登録して定期的に遊びに来てね!
【アニメ関連はこっちから】
びわおちゃんブログをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。